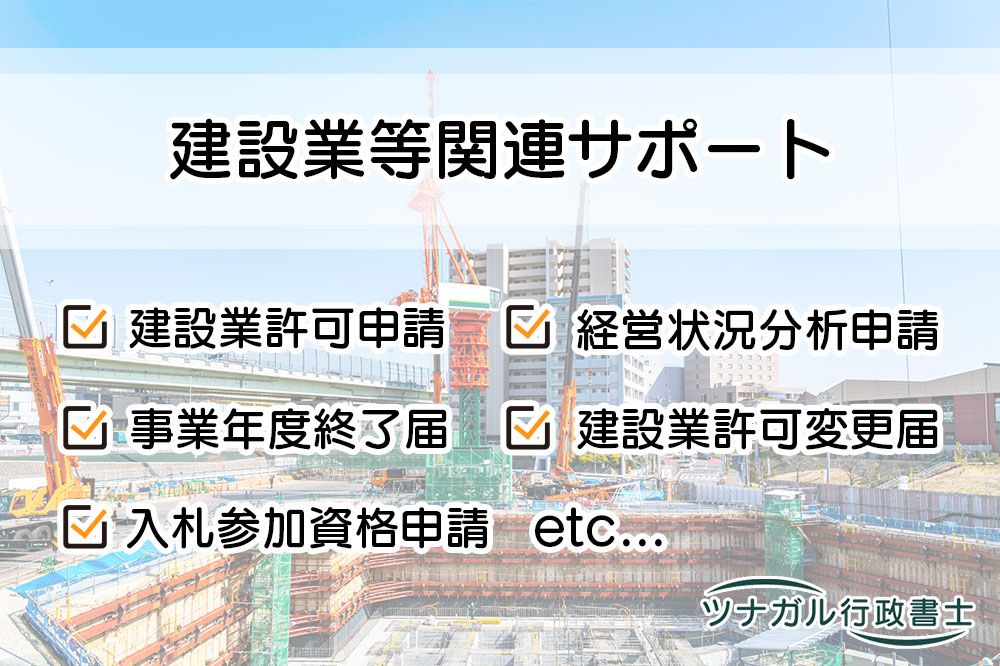建設業関連サポートとは
建設業を始めるには許可の取得が必要であり、その後も継続的な届出や更新、入札への対応など、さまざまな手続きが求められます。では、新規許可から経営事項審査、関連業法の許可取得まで、建設業に関わる幅広い手続きを一括でサポートしています。
【1】建設業許可・維持に関する業務
建設業を始めるには、まず国や都道府県への許可申請が必要です。許可を取得した後も、毎年の決算変更届や、代表者・資本金・本店所在地などの変更手続き、業種の追加申請など、さまざまな届出が求められます。さらに、解体工事業の登録や、技能者の実績管理に活用される「建設キャリアアップシステム(CCUS)」への登録も、事業内容によっては必要です。
【2】経審・経営事項審査関係(公共工事入札を見据えたもの)
公共工事の入札に参加するには、「経営事項審査(経審)」の受審が必須です。経審は、企業の経営状況や技術力などを点数化し、客観的に評価する仕組みで、「経営状況分析(Y点)」や「経営規模等評価(X・Z・W点)」を含みます。申請には多くの書類が必要なうえ、技術者要件や実務経験証明の準備も重要となります。
【3】建設業における技術者・設計事務所関連
設計業務を行う建築士は、事務所の所在地を管轄する都道府県に「建築士事務所登録」を行う必要があります。登録後も、組織変更や担当建築士の交代があれば、随時届出が求められます。また、一定の条件を満たす設計業務を行った場合には、建築士法第23条の6に基づく「設計等の業務に関する報告書」の提出も義務づけられています。
【4】電気・設備等の専門業登録
電気工事を行うには、「登録電気工事業者」としての登録が必要です。これは建設業許可とは別の制度で、専任技術者や営業所の体制、保安管理体制など、独自の要件を満たす必要があります。申請にあたっては、工事の種類や範囲に応じた適切な登録区分を選び、必要書類を整える必要があります。設備工事を始める際には重要な手続きです。
【5】建設工事向けの入札参加資格申請
国や地方自治体が発注する建設工事に参加するには、事前に「入札参加資格」を取得する必要があります。申請には、経審結果や決算書類、会社概要など多くの情報が求められ、提出先によって要件も異なります。手続きの準備やスケジュール管理が重要となるため、初めての方は早めの対応がおすすめです。電子申請に対応している自治体も増えています。
【6】道路使用・占用・特殊車両通行等の申請
建設現場で道路を使用する場合や、資材・重機を大型車両で搬入する際には、道路使用許可や特殊車両通行許可が必要になります。また、道路そのものに構造物を設置するような工事では、道路占用許可や道路法第24条の「自費工事承認」が必要になるケースもあります。現場の開始時期に合わせた早めの申請が、安全でスムーズな工事に欠かせません。
【7】関連業法許可・登録(建設業に附随する業務)
建設業を営む上では、関連法令に基づく許可や手続きも必要になる場合があります。たとえば、工事現場で発生する廃材の運搬を行う場合は「産業廃棄物収集運搬業許可」、外国人技能実習生や特定技能者を雇用する場合は「在留資格」に関する申請が必要です。建設業の実態に応じて、こうした附随業務もあわせて適切に対応することが求められます。