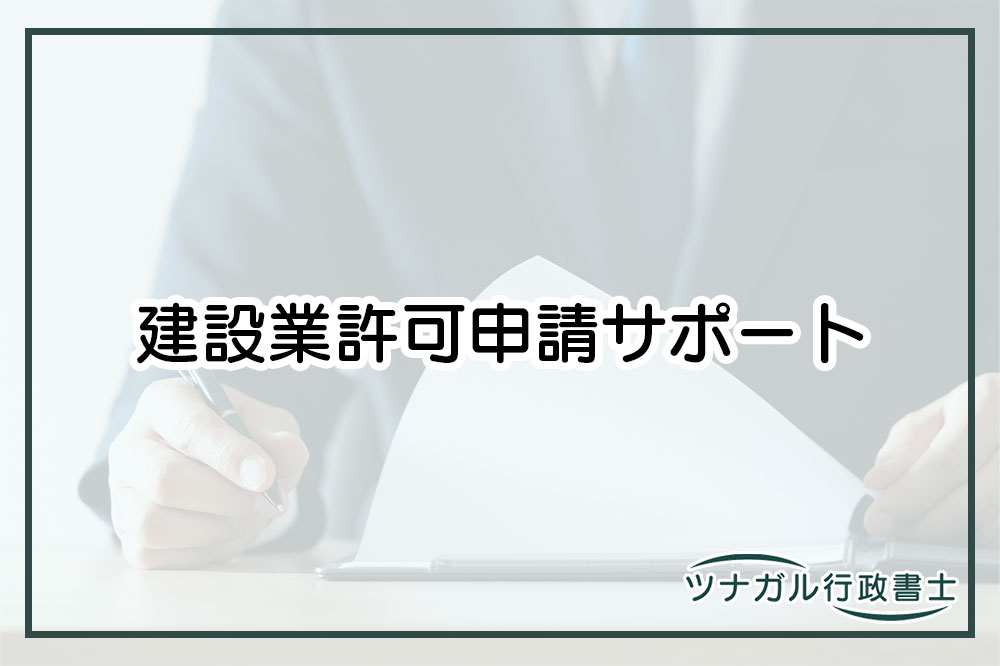料金相場(建設業の許可申請(新規・更新))
新規許可申請
| 許可区分 | 法定手数料 | 報酬代 | 合計金額 | |
| 知事 | 一般 | 90,000 | 165,000 | 255,000 |
| 特定 | 90,000 | 198,000 | 288,000 | |
| 大臣 | 一般 | 150,000 | 220,000 | 370,000 |
| 特定 | 150,000 | 275,000 | 425,000 |
更新許可申請
| 許可区分 | 法定手数料 | 報酬代 | 合計金額 | |
| 知事 | 一般 | 50,000 | 88,000 | 138,000 |
| 特定 | 50,000 | 110,000 | 160,000 | |
| 大臣 | 一般 | 50,000 | 132,000 | 182,000 |
| 特定 | 50,000 | 165,000 | 215,000 |
*日本行政書士会連合会の「報酬額統計」を目安に作成
*行政書士報酬代は目安となります
建設業における許可申請とは
建設業を営むためには、一定規模以上の工事を請け負う際に「建設業許可」が必要となります。許可には「新規許可」と「更新許可」の2種類があり、それぞれのタイミングで適切に手続きを行うことが重要です。以下では、これら2つの手続きについて詳しくご説明します。
建設業新規許可申請
新たに建設業を始める際や、これまで無許可で軽微な工事のみを行っていた事業者が許可が必要な工事を受注するために行う手続きが「新規許可申請」です。この申請は、建設業法第3条に基づき、都道府県知事または国土交通大臣のいずれかから許可を受ける形になります。
ただし、以下のような軽微な工事を行う場合は、許可を取得しなくてもよいとされています。
- 建築一式工事以外:1件の請負代金が500万円未満の工事
- 建築一式工事:1件の請負代金が1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅の工事
無許可で許可対象となる工事を請け負った場合には、以下のような罰則が科される可能性があります。
- 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
- さらに、5年間は新たに建設業許可を取得できなくなる可能性もあります。
建設業許可更新
建設業許可には有効期間があり、原則として5年ごとに「更新申請」を行う必要があります。更新を忘れると許可が失効し、建設業としての営業を継続できなくなります。更新申請は、許可の満了日の30日前までに提出する必要があります。
申請の受付開始時期は、許可の種類によって異なります。
- 都道府県知事許可:満了日の2か月前から受付
- 国土交通大臣許可:満了日の3か月前から受付
また、更新申請には、直近の決算期ごとに提出が義務付けられている「決算変更届」が提出済みであることが前提条件になります。これが未提出の場合、更新申請が受け付けられないこともあるため、注意が必要です。
申請先等
建設業許可は、どのような範囲・内容の工事を行うかによって、申請先や許可の種類が変わります。大きく分けて、「許可を出す行政庁」「工事の種類」「請負金額や体制」によって分類されます。
許可を出す行政庁(申請先)
| 許可の種類 | 営業所の状況 | 申請先 |
| 大臣許可 | 2つ以上の都道府県に営業所がある | 国土交通大臣 |
| 知事許可 | 1つの都道府県内のみに営業所がある | 各都道府県知事 |
* 工事の場所ではなく「営業所の場所」で判断されます。例えば、営業所が東京にしかない場合、全国で工事をしていても「知事許可」でOKです。
一般建設業と特定建設業の区分
元請会社が下請業者に大きな金額の工事を発注する場合、「特定建設業」の許可が必要になります。
| 区分 | 要件 | 主な対象 |
| 特定建設業 | 元請として1件あたり4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)を下請に発注 | 大規模なゼネコンなど |
| 一般建設業 | 上記以外(自社で施工、または下請発注が少額) | 地場の工務店など |
* あくまで「元請が下請に出す金額」が基準です。自社で施工する場合は金額が大きくても一般建設業でOKです
工事の種類(業種)
建設業許可は、行う工事の内容によってさらに「一式工事」と「専門工事」に分かれ、合計29業種に分類されます。
| 業種 | 内容 | 主な工事例 |
| 一式工事(2業種) | 大規模な建築や土木工事をまとめて請け負う | 建築一式工事、土木一式工事 |
| 専門工事(27業種) | 特定の分野に特化した工事 | 電気工事、大工工事、塗装工事、解体工事 など |
* 一式工事の許可があっても、専門工事を行うにはその工事ごとの許可が必要です。
お申込みの流れ
以下は建設業新規許可申請を行政書士に依頼する場合の一般的な流れを、東京都知事許可に依頼した際の流れです。
1. 初回相談・ヒアリング
まずは、お電話やメール、面談等で現在の事業内容や申請予定の業種、過去の実績などについて行政書士が丁寧にヒアリングします。ここで申請要件を満たしているかの簡易チェックも行います。
2. 要件確認・必要書類のご案内
ヒアリング内容をもとに、「経営業務の管理責任者」「専任技術者」「財産的基礎」など、許可要件を満たしているかを確認し、必要な証明書類(登記簿謄本、納税証明、資格証明書など)の一覧をお渡しします。
3. 書類収集と作成
お客様にてご用意いただく資料と、行政書士が取得・作成する書類を整理し、法定の様式に基づいた申請書一式を作成します。東京都の様式・運用に即した対応を行います。
4. 申請前の最終チェック・ご捺印
申請書一式が揃った段階で、内容に不備がないかを最終チェック。お客様には必要な書類にご署名・ご捺印をいただきます(電子申請で行う場合は別途ご案内)。
5. 行政庁(東京都)への申請代行
行政書士が東京都庁の担当窓口に対し、申請を代行します。窓口での質疑応答や補正対応も原則として行政書士が行うため、お客様が直接窓口に行く必要はありません。
6. 審査期間・補正対応
審査には通常、1か月~1.5か月程度かかります。東京都からの確認や追加資料の要求があった場合も、行政書士が窓口となって対応します。
7. 許可証の交付・ご報告
無事に許可が下りると、「建設業許可通知書」が発行されます。行政書士が代理受領またはお客様に郵送され、許可内容や今後の手続き(標識の掲示、事業年度終了後の決算報告など)についてもご案内します。
必要書類
| 書類名 | 新規許可申請 | 更新許可 |
| 経営事項審査の結果通知書 | 〇*1 | × |
| 法人登記簿謄本 | 〇 | 〇 |
| 定款の写し | 〇 | × |
| 直近の決算書 | 〇 | 〇 |
| 納税証明書 | 〇 | 〇 |
| 技術者の資格証明書 | 〇 | 〇 |
| 事業所の賃貸契約書または所有証明書 | 〇 | 〇 |
*1. 公共工事を請負う場合必須
※都道府県によって書式・添付書類が異なる場合があります。不明な点は事前に管轄官署へご確認ください。
案件概要
| 項目 | 内容 |
| サポート内容 | ・必要書類の案内と要件(経営業務管理責任者・専任技術者・財産要件等)の確認 ・該当業種の選定と記載内容の助言 ・申請書類・経歴書の作成と添付資料の整備 ・官公庁への申請書類提出の代行(窓口・郵送・電子) ・審査中の補正対応や許可取得後の手続案内(標識掲示・定期届出等) |
| 依頼者の業務 | ・会社や技術者に関する情報提供 ・必要書類の取得(登記簿謄本、納税証明書、資格証など) ・作成された書類への署名・押印 ・追加資料のご提供(必要時) |
| 申請期間(目安) | 1.5〜2か月程度(書類準備〜審査完了まで) |
| 対応地域 | 全国オンライン対応可 |
| 相談方法 | メール・電話・オンライン面談可 |
| お支払い方法 | クレジットカード、銀行振込 |
| お支払い金額 | 着手金:報酬の50%(業務開始前) 完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等) |
| お支払い期限 | 着手金:業務開始前にお支払い 完了金:許可取得・納品時にお支払い |
| キャンセル料 | 着手前まで無料 |
行政書士に依頼するメリット
建設業の許可申請は、法律に基づいた複雑な書類作成や添付資料の準備が必要で、要件の確認や申請先ごとの対応も細かく分かれています。行政書士に依頼すれば、必要書類の収集から申請書の作成、役所とのやりとりまでを一括でサポートしてもらえるため、手間や時間を大幅に削減できます。また、要件の不備による申請却下を防ぐための事前チェックや、今後の更新時期の管理なども任せられるため、事業に専念できる安心感があります。