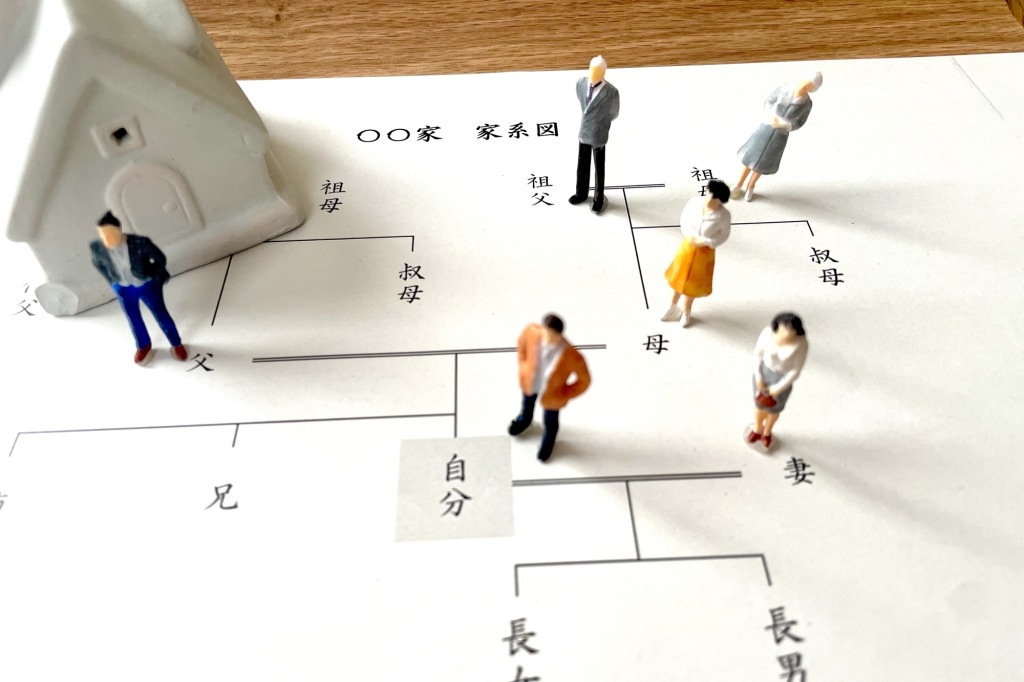目次
はじめに
世界でも有数の長寿国である日本は、高齢化率が29%を超え、国民の約3人に1人が65歳以上という社会に突入しています。こうした背景から、遺産相続に関する手続きはますます身近で重要なテーマとなっています。
実際、政府の統計によると、2024年は約160万人が亡くなっており、そのたびに相続手続きが発生しています。国税庁の発表では、相続税の課税件数は年間約12万件に達し、課税割合は全体の約9%程度とされています。大多数の家庭では相続税の申告が不要である一方、相続人の確定や不動産登記、銀行口座の名義変更といった実務手続きは、多くのケースで必要になります。
相続に関する手続きの多くは法律や制度に基づき行わなければならず、誤った対応や遅延は後々のトラブルに直結する可能性があります。例えば、不動産登記を放置したまま相続人が亡くなれば権利関係がさらに複雑化し、相続人の数が増加して合意形成が困難になるケースが実際に報告されています。
また、家庭裁判所の統計では、相続を巡る「遺産分割事件」は年間で16,000件以上が申し立てられており、家族間の争いに発展する例も少なくありません。こうした背景を踏まえると、相続に関する手続きをあらかじめ理解し、トラブルを未然に防ぐことが大切であることが分かります。行政書士や司法書士、税理士、弁護士といった士業は、それぞれの専門分野に応じて相続手続きをサポートできる体制を整えており、適切な相談先を見極めることでスムーズな手続きが可能になります。
本記事では、代表的な遺産相続手続きの流れ、士業の役割、自分で行える範囲、そして必要となる費用の目安について、詳しく解説します。高齢化社会において避けて通れない相続の問題を正しく理解し、皆さまが安心して準備を進められる一助になれば幸いです。
代表的な遺産相続手続き
遺産相続は、被相続人(亡くなった方)の財産の状況によっては多くの手続きが必要になります。ここでは、一般的に行われる主要な相続手続きについて解説します。
相続人と相続財産の確定
相続手続きの最初のステップは、誰が相続人であるのか、そしてどのような財産が遺されているのかを明らかにすることです。そのために、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を収集し、法定相続人を確定させます。相続人の数が多い場合や家族関係が複雑な場合には、「相続関係説明図」を作成しておくと相続人が整理しやすく、さらにその後の手続きにおいても役立ちます。
また、不動産、預貯金、有価証券、保険金、さらには負債も含めた相続財産を一覧化した「財産目録」を作成することも重要です。財産の調査は、不動産登記簿や固定資産税納税通知書の確認、銀行や証券会社への残高照会、保険会社への問い合わせ、さらにはクレジットカードやローン明細の調査などを通じて行い、漏れのないように注意しなければなりません。
遺産分割協議
相続人が複数いる場合、財産の分け方を決定するために遺産分割協議を行います。ただし、遺産分割協議はすべてのケースで必須ではなく、例えば、被相続人が遺言書を残しており、その内容に従って相続を行う場合には協議を行う必要はありません。
協議には相続人全員の参加が必要で、合意内容を「遺産分割協議書」として書面化することが望まれます。ここで作成した遺産分割協議書は、不動産登記や銀行の預金解約・名義変更など、外部の機関での手続きに利用する際に必要になります。不動産や預貯金の名義変更を伴わない場合は、必ずしも協議書の作成は求められませんが、将来的なトラブルを防ぐために作成しておくことが一般的です。
また、相続人の中に行方不明で連絡が取れない人がいる場合、まずは戸籍の附票や住民票の除票を通じて所在の確認を試みます。それでも見つからなければ、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てる方法があります。不在者財産管理人が選任されれば、その人物が協議に参加することになります。
なお、相続人同士の話し合いで協議がまとまらない場合には、家庭裁判所で「調停」が行われます。調停は相続人の誰からでも申し立てることができ、裁判官と調停委員が中立的な立場で話し合いを仲介します。調停には数千円程度の手数料が必要で、弁護士を代理人とする場合にはその報酬が別途発生します。調停は1回で終わることは少なく、数か月から半年以上かかることもあります。この調停でも合意に至らなければ最終的には「審判」に移行し、裁判所が分割方法を決定します。
遺言執行
被相続人が遺言を残していた場合、その内容に基づき相続が行われます。まず遺言書を発見した場合には、家庭裁判所で「検認」という手続きを経て開封する必要があります(公正証書遺言の場合は検認不要)。検認とは、遺言の有効性を確認するものではなく、改変を防止するために行われる手続きです。検認を経たのち、遺言の内容に従って遺産の分配や名義変更が進められます。
遺言執行者が指定されている場合は、その人物が中心となってこれらの手続きを実施します。遺言執行者が指定されていない場合には、相続人の合意により選任するか、家庭裁判所に選任を申し立てる必要があります。家庭裁判所が選任する場合、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれることが多いですが、相続人の中から選ばれることもあります。執行者は中立的な立場で、遺言内容を忠実に実現する役割を担います。
不動産の相続登記
土地・建物といった不動産を相続した場合、名義変更を行う相続登記が必要です。令和3年の法改正により、相続発生から3年以内に登記を行うことが義務付けられました。正当な理由なく相続登記を怠った場合は、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。
相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局で行い、申請は相続人自身が行うことも、司法書士に依頼することも可能です。申請方法は、窓口での提出のほか、オンライン申請システムを利用することもできます。オンライン申請は、相続した物件が遠方にある場合や、平日の日中に時間が取れない方などにとっては大変便利な方法です。なお、手続きの際の必要書類には、被相続人の戸籍一式、相続人全員の印鑑証明書、遺産分割協議書などが含まれます。
また、相続登記には登録免許税という手数料がかかります。金額は不動産の固定資産税評価額の0.4%で計算されるのが原則であり、例えば評価額が2,000万円の不動産の場合、8万円の登録免許税が必要となります。その他、書類の取得費用や専門家に依頼した場合には報酬がかかります。
銀行の預金相続
口座名義人の死亡の届出を受けた金融機関は、速やかに口座を凍結します。これは、相続人による不正な引き出しやトラブルを防ぐためであり、金融機関は相続人全員の合意を確認するまで出金を認めません。そのため、たとえ家族が被相続人の口座暗証番号を知っていてATMから引き出せたとしても、不正出金とみなされ、後々返還や法的責任を問われる可能性があります。
預金相続手続きに際しては、遺産分割協議書や戸籍一式、相続人全員の印鑑証明書などを提出する必要があり、一部の銀行では法務局で作成した「法定相続情報一覧図」によって手続きを簡略化できる場合もあります。また、申請から実際に払い戻しがされるまでの日数は、金融機関や手続きの状況によって差がありますが、おおむね1週間から1か月程度を要します。
自動車の相続
自動車を相続する場合は、陸運支局で名義変更の手続きを行います。名義変更を行わないまま使用すると、税金の支払いや自動車保険の手続きの際にトラブルにつながる恐れがあるため、早めの対応が望まれます。
2025年時点で、相続による名義変更はオンライン申請(OSS申請)には対応しておらず、運輸支局窓口での手続きが必要です。普通自動車の場合、必要書類には車検証、相続人の戸籍謄本、印鑑証明書、遺産分割協議書などがあります。さらに、名義変更の手続きを行う前に、相続人の住所地を管轄する警察署で車庫証明を取得しておく必要があります。
なお、相続による名義変更をしてもナンバープレートはそのまま使用できますが、管轄する陸運支局が変わる場合にはナンバープレートも変更する必要があります。また、自動車の相続手続きには名義変更手数料や車庫証明申請手数料がかかり、合計で数百円から数千円程度必要となるのが一般的です。行政書士などの専門家に依頼した場合には別途報酬が必要となります。
相続税の申告
相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合には相続税の申告が必要です。申告期限は相続開始から10か月以内であり、税務署に対して所定の申告書を提出しなければなりません。申告は相続人全員がそれぞれ行う必要はなく、相続人代表が相続人ごとの負担額を計算して申告書に記載することが可能です。もっとも、各相続人が別々に申告を行うことも可能です。
申告にあたっては、遺言書や遺産分割協議書、被相続人と相続人の戸籍謄本、財産目録、預金残高証明、不動産の固定資産税評価証明書など、多数の書類を準備する必要があります。これらは財産や分割方法を明らかにするための重要な資料となります。なお、動産(貴金属類、ブランド品、美術品など)の評価は、一般的に市場価格や鑑定人の査定を基準として行われます。特に美術品や骨董品については、評価額が相続税額に大きく影響するため注意が必要です。
税理士に依頼する場合は、申告期限から逆算して半年程度前には相談を開始するのが安心です。相続財産の内容確認や評価、分割協議に時間がかかるケースもあるため、早めの準備が求められます。
遺産相続手続きにおける士業の役割
遺産相続に関する手続きは、専門家ごとに対応できる範囲が異なります。
以下の表は、代表的な手続きと各士業の対応可否を整理したものです。
| 手続き内容 | 行政書士 | 司法書士 | 税理士 | 弁護士 |
| 相続人調査(戸籍収集) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 相続関係説明図・ 法定相続情報一覧図の作成 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 相続財産の調査 (登記簿・残高証明等の収集) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 遺産分割協議書の作成 | 〇 | 〇 | △※1 | 〇 |
| 遺産分割協議に 代理人として参加 |
× | × | × | 〇 |
| 不動産の相続登記 | × | 〇 | × | 〇 |
| 預金・株式等の相続 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| 自動車の名義変更 | 〇 | × | × | × |
| 相続税の申告 | × | × | 〇 | △※2 |
| 相続放棄の申し立て | × | △※3 | × | 〇 |
| 遺産分割をめぐる 紛争解決・調停代理 |
× | × | × | 〇 |
※1 相続税の申告に必要な場合のみ
※2 国税局長に税理士業務を行う旨通知した弁護士のみ可
※3 書類作成のみ
相続手続きを全て自分で行うことはできる?
相続手続きは法律で「必ず専門家に依頼しなければならない」と定められているわけではなく、基本的には相続人自身が自分で行うことが可能です。例えば、相続人の確定のための戸籍収集や財産の調査、銀行や証券会社への名義変更手続き、不動産の相続登記の申請なども本人が手続きを行うことは制度上認められています。
相続財産の種類が少なく単純なケースであれば自分で対応できる場合もありますが、財産が不動産・預貯金・有価証券・動産(貴金属類、美術品など)のように多岐にわたると難易度は格段に上がります。このようなケースでは、実際にすべての手続きを自分で行うのは容易ではありません。
特に、不動産の相続登記は専門的な知識や多くの添付書類が必要となり、誤りがあると法務局から修正を求められることになります。また、相続税の申告や納税については税務に関する専門的知識が不可欠であり、申告漏れや評価誤りがあれば追徴課税のリスクも生じます。さらに、相続人間で意見がまとまらない場合には家庭裁判所での調停や審判に発展することがあり、この場合には弁護士でなければ代理できません。
このように、手続き自体は自分で進められる一方で、専門知識の不足や時間的・精神的な負担から、行政書士や司法書士、税理士、弁護士といった専門家に依頼するケースが多いのが実情です。自分で行う場合と専門家に依頼する場合のメリット・デメリットをよく理解した上で、状況に応じて適切な選択をすることが重要です。
相続手続きにかかる費用
遺産相続に関する手続きでは、書類の取得や登記、税務申告などに伴ってさまざまな費用が発生します。ここでは大きく「法定手数料」と「専門家に依頼する場合の費用」に分けて解説します。
法定手数料
相続手続きを進める際には、まず役所や法務局などで取得する公的書類や登記にかかる費用といった「法定手数料」が発生します。これらは専門家への委任の有無に関わらず必要となる費用であり、避けて通ることはできません。
以下に代表的な手数料を紹介します。
- 戸籍謄本、除籍謄本、住民票の除票、戸籍の附票などの取得費用:300~450円程度/1通(自治体により異なる)
- 不動産の相続(登録免許税):不動産の固定資産税評価額の0.4%
- 預金相続:数百~数千円程度(銀行により異なる)
- 自動車の相続(名義変更手数料・車庫証明申請費用):合計で3,000円程度(地域により異なる)
専門家依頼する場合にかかる費用
相続に関する手続きをすべて自分で行うことも可能ですが、専門知識が必要となる場面では士業に依頼するケースが一般的です。
以下の表に、各専門家の主な業務内容と費用の目安を示します。なお、費用は依頼する手続きの複雑さによって大きく変わりますので、正確な金額を知りたい方は見積もりを取って確認してください。
| 専門家 | 主な業務内容 | 費用の目安 |
| 行政書士 | 相続人調査、遺産分割協議書作成 | 数万~十数万円程度 |
| 司法書士 | 不動産の相続登記 | 5万円~15万円程度 |
| 税理士 | 相続税申告 | 相続財産の0.5~1.5%程度 |
| 弁護士 | 紛争対応、調停・訴訟代理 | 数十万~数百万円程度 (着手金・報酬金制度が一般的) |
まとめ
遺産相続の手続きは、相続人や財産の確定から始まり、遺産分割協議、不動産や預金の名義変更、税務申告に至るまで多岐にわたります。
相続手続きは相続人自身で行うことも可能ですが、財産が複雑で多岐にわたる場合や相続人間で意見が分かれる場合には専門家の関与が不可欠です。ぜひ今回解説した内容を参考に、どの部分を自分で進め、どの部分を専門家に依頼するか検討してみてください。適切なサポートを受けることで、円満な相続を目指しましょう。
関連コラムはこちら↓
遺言書作成サポートは行政書士におまかせ!法的効力を持つ遺言書のポイント遺産分割協議書とは?行政書士がサポートする作成手順と注意点相続人調査は行政書士におまかせ!相続トラブルを防ぐポイントや必要書類を詳しく解説

特定行政書士として、幅広い業界における法務支援やビジネスサポートに従事するとともに、業務指導者としても精力的に活動。企業法務や許認可手続きに関する専門知識を有し、ビジネスの実務面での支援を中心に展開しています。(登録番号:03312913)