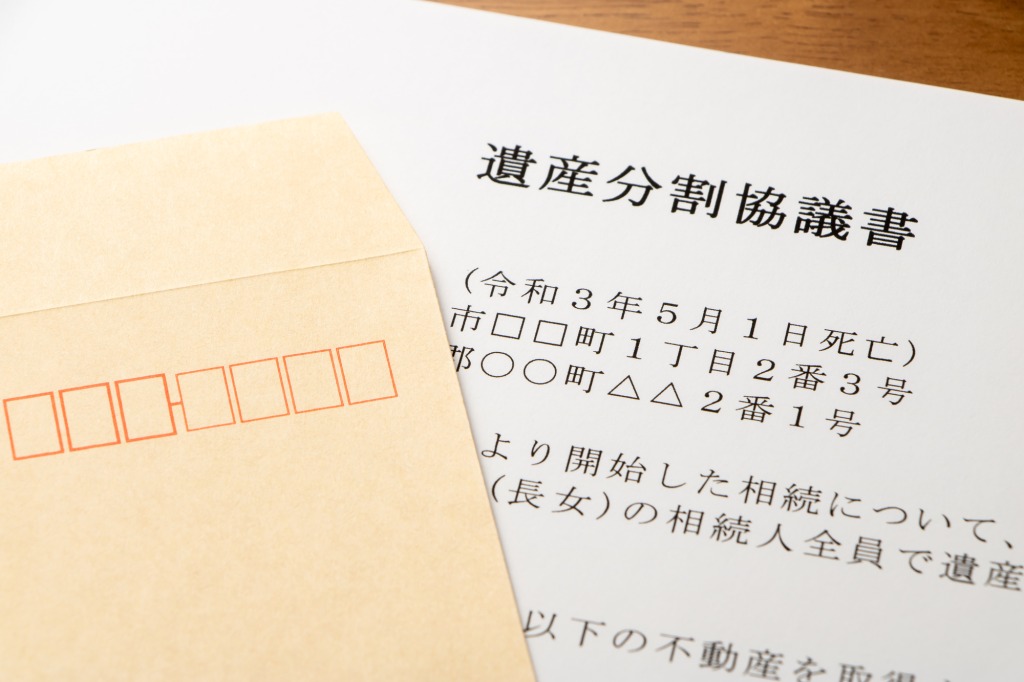遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、相続人全員が集まって行う「遺産分割協議」で決定した内容をまとめた文書のことです。相続人が複数いる場合には、誰がどの財産を相続するのかを明確にしておかないと、後にトラブルにつながる可能性があります。
ここでは「遺産分割協議書を作成する場面」「作成期限の有無」「参加者の範囲」について解説します。
遺産分割協議書は必ず作成しなければいけない?
遺産分割協議が必要となるのは、例えば遺言書が存在せず、かつ法定相続分とは異なる割合で分割を行う場合です。また、遺言書があってもその内容とは異なる方法で分割したい場合には、相続人全員が合意することによって別の分割方法を決めることができます。さらに、遺言書にすべての財産が記載されていない場合、つまり一部の財産しか指定されていない場合には、残された財産の分割方法を新たに協議しなければなりません。
一方で、遺言書がなく法定相続分に従って分割する場合や、遺言書の記載通りに分割を行う場合には、協議を行う必要はありません。
このように、遺産分割協議は相続人同士の合意を形成するために不可欠な場面で行われ、協議の結果をまとめるために協議書が作成されるのが一般的です。
遺産分割協議書に作成期限はある?
遺産分割協議書そのものに法律上の作成期限は設けられていません。しかし、実際には相続税の申告期限である「被相続人の死亡の日の翌日から10か月以内」に作成することが推奨されます。なぜなら、遺産分割協議を行っていないまま相続税の申告を行うと、相続税の額を低くする特例(配偶者の軽減税率など)を適用できず、高額の納税を行うことになるからです。
もしも申告期限までに遺産分割協議がまとまらなかった場合、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告を行えば、3年以内に遺産分割が成立した後、遡って特例の適用が可能です。しかしながらこの手続きの場合は、一旦高額な納税を行う必要があり、また還付の手続きも複雑になるため、できる限り相続税の申告期限までに分割協議をまとめるのが良いでしょう。
特に相続人の数が多い場合には、話し合いのスケジュール調整に難航したり、それぞれの相続人に主張があったりして、合意に至るまでに予想以上に時間がかかってしまう場合があります。ご家族が亡くなられて辛い中ではありますが、遺産分割協議はできるだけ早めに始めるのが望ましいと言えるでしょう。
「遺産分割協議」には誰が参加する?
遺産分割協議には、相続人全員が参加する必要があります。1人でも欠けた状態で行われた協議は無効となるため、相続人の確認作業がとても重要です。
相続人は亡くなった方の家族構成によって変わりますが、配偶者・子ども(養子含む)・直系尊属(父母・祖父母)・兄弟姉妹・認知した婚外子などが該当する可能性があり、相続人には法定相続分に基づいて権利が発生します。場合によっては、代襲相続人(亡くなった相続人の子ども)が含まれることもあります。また、協議の場には相続人以外の人、例えば未成年者の代理人や成年後見人が参加することもあります。
遺産分割協議書の用途
遺産分割協議書は、相続人全員が合意した内容を証明するための重要な書類であり、相続手続きを進めるうえで幅広く利用されます。
まず、不動産の名義変更の際に法務局で登記を行うためには、相続人全員の署名・押印がある遺産分割協議書が求められます。また、銀行口座の解約や残高の払い戻しを行う場合にも、この協議書の提出を求められることが多くあります。
さらに、相続税の申告をする際には、遺産をどのように分割したのかを明確に示す資料として遺産分割協議書が役立ちます。未分割のまま申告すると、税務上の不利益を被る可能性があるため、協議書を整えてから申告を行うことが推奨されます。
加えて、遺産分割協議書は相続人間の合意を明文化する役割を持ち、後のトラブル防止にもつながります。口頭での合意だけでは解釈の相違が生じやすいため、明確な書面を残しておくことで、将来の紛争を未然に防ぐことができます。特に不動産や金融資産のように価値が大きい財産については、協議書の存在が相続人全員の安心につながるのです。
遺産分割協議書に記載する内容
遺産分割協議書は、相続人全員が合意した内容を証明するための重要な文書です。作成にあたっては、いくつかの基本的な事項を漏れなく記載することが求められます。以下に代表的な内容を解説します。
被相続人(亡くなった方)の情報
協議書の冒頭には、被相続人の氏名、生年月日、死亡日、本籍地、最後の住所地などの基本情報を記載します。これにより、どの方の遺産についての協議なのかが明確になります。戸籍や住民票などの情報と一致する形で記載することが望ましいです。
相続人全員が決定した内容に合意していること
協議書には、相続人全員が話し合ったうえで決定した内容に合意している旨を明記します。協議に参加していない相続人がいる場合は無効となるため、必ず「相続人全員で協議した結果」であることを文章にしておく必要があります。具体的には、以下のような文章を記載するのが一般的です。
「被相続人○○の遺産相続につき、被相続人の妻○○、被相続人の長男○○、被相続人の長女○○の相続人全員が協議を行い、以下の通り被相続人の遺産を分割することで合意した。」
財産の具体的な内容と分割方法
相続財産の一覧を具体的に記載し、それぞれをどの相続人が取得するのかを明確に示します。土地や建物であれば登記簿に記載のある通りに書き写し、預貯金であれば金融機関名や口座番号・口座名義、株式であれば証券会社名や銘柄・数量などをできるだけ詳しく書きます。
あとで別の財産(債務)が見つかったときの対応方法
協議書に記載されなかった財産や債務が後日判明することもあります。その場合にどう対応するかを事前に決め、協議書に記載しておくと安心です。具体的には、以下のような文章を記載しておくと良いでしょう。
- 「本協議書に記載のない遺産が判明した際は、その部分についてのみ改めて相続人全員で協議する。」
- 「本協議書に記載のない遺産が判明した際は、その全てを被相続人の妻○○が相続する。」
合意した日付
協議書には日付を明記することも欠かせません。この場合、「令和七年八月吉日」などの曖昧な表記ではなく、「令和7年8月1日」のように明確に年月日を記載しましょう。なお、ここに記載する日付は「合意が成立した日」とするのが一般的ですが、法律上の規定などは特にありません。そのため、合意が成立した日がはっきりとしない場合には、協議書を作成した日や、相続人全員の署名が揃った日などにしても構いません。
相続人全員の情報
最後に、相続人全員が氏名(自著)・生年月日・住所を記載し、実印の押印も行います。これにより、協議書の真正性が担保されます。
遺産分割協議書を作成するための準備
遺産分割協議書をスムーズに作成するためには、事前の準備が欠かせません。ここでは、特に重要な相続人と財産の整理について解説します。
相続人の整理
まず行うべきは相続人の確定です。相続人の範囲は民法で定められており、被相続人の配偶者は常に相続人となり、そのほかは子ども、直系尊属(父母や祖父母)、兄弟姉妹の順に相続人となります。誰が相続人にあたるのかを正確に確認するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集する必要があります。これを通じて、認知された子どもや代襲相続人(すでに亡くなった子の子ども)がいるかどうかも確認できます。相続人が1人でも欠けていると協議そのものが無効となってしまうため、関係性が複雑な場合には専門家への相談も検討しましょう。
財産の整理
相続人が確定したら、次に遺産の範囲を明らかにします。遺産には不動産、預貯金、株式、動産(自動車や貴金属など)、さらには負債(借金やローン)も含まれます。不動産については登記簿謄本を取得し、預貯金については金融機関から残高証明書を取り寄せます。株式や投資信託などの有価証券は証券会社からの取引残高報告書で確認し、負債については借入先の金融機関やクレジットカード会社からの明細を整理します。遺産協議を行うまでの間に、これらすべてを一覧にした「財産目録」を作成しておきましょう。
様々な状況下での遺産分割協議
遺産分割協議は相続人全員が集まって合意形成を行うのが原則ですが、現実には様々な事情によりスムーズに進められない場合があります。ここでは代表的な特殊ケースと、その際に必要となる対応方法を解説します。
未成年の相続人がいる場合
相続人に未成年者が含まれる場合、未成年者は法律行為を単独で行えないため、通常は親権者が代理人として協議に参加します。ただし、その親権者自身も相続人となっている場合は「利益相反」となるため、子の代理人となることはできません。典型的な例としては、父親が亡くなり、母親と未成年の子が相続人となるケースです。
このようなケースでは、家庭裁判所に申し立てをして「特別代理人」を選任する必要があります。特別代理人の選任に関する申立ては、未成年者の親権者(=利益相反の当事者である親)が申立人となるのが一般的ですが、状況により、未成年後見人や親族などの利害関係人が申立てを行うことも可能です。選任される特別代理人は、弁護士や司法書士などの第三者が選ばれることもあれば、祖父母や叔父叔母などの親族が選ばれることもあります。選任までにかかる期間は事案によって異なりますが、概ね2~6週間程度が目安となります。
一方で、親が相続人ではない場合、例えば父方の祖父が亡くなり、孫が未成年でその父(亡くなった人の子)は既に死亡しているケースでは、その未成年の孫の母親は相続人に含まれないため、利益相反にはならず代理人として協議に参加できます。
話し合いによる合意ができない場合
相続人同士で意見が対立し、合意に至らない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることになります。調停では裁判官と調停委員が中立的な立場から関与し、当事者同士の意見を調整します。申し立てができるのは相続人や受贈者などの利害関係人です。
調停は1回で終わることは少なく、月1回程度の頻度で複数回開かれるのが一般的です。事案の複雑さにもよりますが、調停開始から合意形成までの期間はおおむね半年から1年程度を要するケースが多いといえます。話し合いがまとまらなければ、最終的に「審判」に移行し、裁判所が分割方法を決定します。
当事者として調停に臨む場合、自分で対応することも可能ですが、専門的な知識や交渉力が求められるため、弁護士を代理人にすると安心です。弁護士は、証拠の提出や調停委員への説明を適切に行ってくれるため、複雑な事案や感情的な対立が強い場合には特に有効です。
相続人の所在が分からない場合
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があることは先に解説しましたが、相続人の中に所在不明な人がいると、話し合いを進めることができません。このようなケースでは、まずは一般的な方法として、戸籍の附票や住民票の除票を取り寄せる、親族や勤務先に照会するなどの方法で相続人の所在調査を行います。これらの調査によって所在が判明すれば、協議に参加してもらうよう連絡を取りましょう。
しかし、あらゆる手を尽くして探しても相続人の所在がわからない場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てる必要があります。不在者財産管理人は、所在不明の相続人の利益を代弁する形で遺産分割協議に参加することができます。選任されるのは、相続人と利害関係が少なく中立性が保てる人物であることが望ましいため、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれるケースが多いです。ただし、親族の中で適任者がいれば選任されることもあります。選任にかかる期間は事案の複雑さや家庭裁判所の混雑状況によって異なりますが、申立てから2か月前後で選任審判が確定するのが一般的です。
相続人同士が遠方に住んでいる場合
相続人が全国各地や海外に散らばっている場合、物理的に一箇所に集まることが難しいケースもあります。遺産分割協議は必ずしも同じ場所に集まって行う必要はなく、電話やビデオ通話、メールや手紙で合意を形成することも法的に有効です。重要なのは、相続人全員が同じ内容に合意していることです。
協議の結果をまとめた遺産分割協議書については、署名・押印を郵送でやり取りする方法が広く実務で用いられています。相続人ごとに協議書を回覧し、署名・押印をして次の相続人に送付する形で進めることが可能です。ただし、訂正が生じた場合は全員が再署名・押印を求められることになるため、内容を十分に確認したうえで署名に臨むことが重要です。
また、相続人の中に海外在住で帰国が難しい人がいる場合には、在外公館(大使館・領事館)で署名証明書(サイン証明書)を添付する方法が一般的です。これは、日本に住民票がない方は市区町村が発行する印鑑証明書を取得できないため、その代替となる証明書が必要となるからです。
なお、ここでいう「署名証明(サイン証明)」とは、在外公館(大使館・領事館)がその人物の署名が真正であることを公的に証明する書類のことです。このように署名証明を受けた遺産分割協議書を国際郵便で日本に送付することで、海外にいながら協議に参加することが可能になります。
相続人が刑務所に収容されている場合
服役中の相続人も当然に相続権を持ち、遺産分割協議に参加する必要があります。このようなケースでは、まず面会や手紙などを通じて、遺産の分割方法について本人の合意を取り付けなければなりません。そのうえで、協議の内容を反映した遺産分割協議書を作成し、刑務所へ郵送します。
その後、服役中の本人が協議書に署名をし、実印の代わりに拇印を押します。刑務所での実印の押印や印鑑証明書の取得は事実上不可能であるため、このような方法を取るのが一般的です。さらに、本人が刑務所長に申告し、拇印が本人のものであることを証明するための「奥書証明(おくがきしょうめい)」を発行してもらいます。この奥書証明を添付することで、遺産分割協議書の有効性が担保されます。
遺産分割協議書の作成にかかる費用
遺産分割協議書を作成する際にかかる費用は、大きく分けて「法定費用」と「専門家に依頼した場合の費用」に分けられます。ここでは、それぞれの費用の概要を解説します。
法定費用など
遺産分割協議書そのものを作成することに対して、国や自治体に納める法定費用はありません。つまり、協議書を自分たちで作成する場合、作成自体に手数料はかからないのです。
ただし、協議書に添付する書類の取得には、下記のような手数料が必要になります。
- 戸籍謄本(被相続人と相続人全員のもの):450円/1通
- 戸籍の附票(被相続人のもの):300円/1通(自治体により異なる)
- 印鑑登録証明書(相続人全員のもの):300円/1通(自治体により異なる)
- 不動産の登記簿謄本:600円/1通
- 口座残高証明書:550~1,100円/1通(金融機関により異なる)
行政書士に依頼する場合の費用
行政書士に遺産分割協議書の作成を依頼する場合は、行政書士報酬がかかります。報酬は相続人の数や財産の種類・数などによって異なりますが、一般的には3万円〜10万円程度が目安とされています。行政書士に依頼することで、戸籍謄本などの必要書類の収集まで任せられることや、法的に抜け漏れのない正確な書面を作成できることなどのメリットがあります。
ただし、行政書士の業務範囲は「書類の作成とその手続き代行」に限られます。したがって、特定の相続人の代理人として遺産分割協議に参加したり、相続人同士で争いがある場合の紛争解決に介入したりすることはできません。また、相続放棄の手続き(家庭裁判所への申述)、相続登記(法務局への不動産登記申請)、相続税の申告(税務署への申告)は、それぞれ司法書士や弁護士、税理士といった他士業の専門領域になります。
まとめ
遺産分割協議書は、相続人全員が合意した内容を明文化し、不動産登記や銀行手続き、相続税申告などを円滑に進めるために必要な書類です。
相続は人生の中でそう何度も経験するものではなく、戸惑いや不安を伴うものです。だからこそ、早めに準備を始め、必要に応じて行政書士などの専門家のサポートを受けながら進めることが大切です。遺産分割協議書を正しく作成し、スムーズな相続手続きにつなげることが、円満な相続の第一歩となるでしょう。
関連コラムはこちら↓
遺言書作成サポートは行政書士におまかせ!法的効力を持つ遺言書のポイント遺言書の種類を徹底解説!法的効力の違いや作成時の注意点行政書士が解説!エンディングノートの作成方法と押さえるべきポイント

特定行政書士として、幅広い業界における法務支援やビジネスサポートに従事するとともに、業務指導者としても精力的に活動。企業法務や許認可手続きに関する専門知識を有し、ビジネスの実務面での支援を中心に展開しています。(登録番号:03312913)