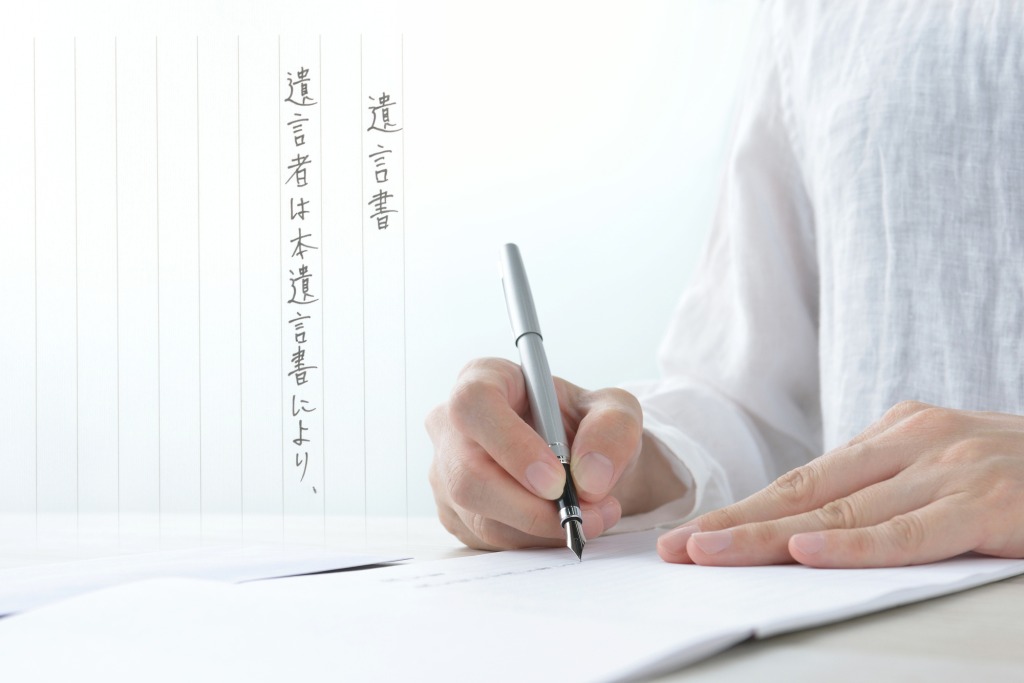目次
はじめに
「遺言」という二文字は日常の様々な場面で目にすることがありますが、「ゆいごん」と「いごん」という二つの読み方があることをご存じでしょうか?実は、一般的な日常会話では「ゆいごん」、法律の条文や専門的な文脈では「いごん」のように使い分けられているのです。
近年、日本では高齢化が進み、相続や遺産に関する関心がますます高まっています。総務省の統計によると、65歳以上の高齢者は人口の約3割を占めており、多くの方が「自分の財産をどのように引き継ぐか」を現実的な課題として考え始めています。また、裁判所の統計によれば、遺産分割事件の3分の1以上は相続財産が1,000万円以下の比較的少額のケースで発生しており、財産の多寡にかかわらず相続トラブルは起こりやすいことが分かります。つまり、遺言書は「資産が多い人だけのもの」ではなく、誰にとっても必要な備えといえるのです。
本記事では、遺言書の種類や書き方、文章例、保管方法、作成にかかる費用までを幅広く解説します。自分や家族の未来のために、遺言書という準備を前向きに考えるきっかけにしていただければ幸いです。
遺言書の種類
遺言書には大きく分けて3つの種類があり、それぞれ作成方法や効力、利用のしやすさが異なります。ここでは、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の特徴について解説します。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が自ら全文、日付、氏名を手書きし、押印することで成立する最も手軽な遺言方式です。近年は財産目録についてパソコンで作成したものや通帳のコピーを添付することも認められ、利用しやすくなっています。
費用がほとんどかからない点が大きなメリットですが、形式の不備があると無効になる可能性があるため注意が必要です。また、相続発生時には家庭裁判所での検認手続きが必要となる点も押さえておきましょう。ただし、後述する法務局による自筆証書遺言保管制度を利用して保管している場合には、この検認手続きは不要となります。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が関与して作成される遺言です。遺言者が公証役場に出向き、公証人に口述した内容を文書化してもらい、署名押印することで成立します。
公正証書遺言は、原本が公証役場で厳重に保管されるため、偽造や紛失の心配がなく、検認手続きも不要です。作成には証人2名の立会いと手数料が必要ですが、確実性の高さが最大のメリットです。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言内容を秘密にしたまま公証役場で存在を確定させる方式です。遺言者が作成した文書に署名押印し、封印をしたうえで公証人と証人2名の前で提出することで成立します。
秘密証書遺言はあくまで「遺言の存在」を公的に証明する仕組みであり、内容そのものを公証人が確認するものではありません。そのため、形式不備があれば無効となる可能性は残り、相続発生時の検認手続きも必要です。
公正証書遺言に比べるとメリットは少なく、実務上は利用がほとんど見られませんが、「内容は絶対に秘密にしたいが遺言の存在は公式に残しておきたい」という特殊なニーズに対応する制度といえます。
自筆証書遺言の構成と文章例
遺言書は大きく分けて5つの構成要素から成り立っています。それぞれの部分には役割があり、適切に書くことで遺言の効力が確実になります。
ここでは、自筆証書遺言の構成と各項目の文章例を紹介します。
①前文
前文は遺言者が自分の意思で遺言を作成することを示す部分です。自分の氏名や生年月日を明記し、遺言の趣旨を簡潔に述べます。
文章例
「遺言書
私、○○(昭和○年○月○日生)は、自己の自由意思に基づき、本遺言書により以下のとおり遺言する。」
②本文
本文には、具体的な財産の分配方法や遺贈の内容を記載します。誰に何を相続または遺贈するかを明確に書きます。
文章例
「私の所有する自宅建物(所在地:東京都○区○町○番地)およびその敷地を妻○○に相続させる。
私の所有する賃貸用不動産(所在地:神奈川県○市○町○番地)およびその敷地をを長男○○に相続させる。
私の所有する別荘(所在地:長野県○市○町○番地)およびその敷地を長女○○に相続させる。
私の所有する株式(株式会社○○○○、株数○○株)を次男○○に相続させる。
その他の預貯金については、全額を妻○○に相続させる。」
③遺言執行者の指名(任意)
遺言執行者を指定することで、遺言の内容を確実に実行してもらえます。信頼できる人物や専門家を選ぶのが一般的です。
文章例
「本遺言の執行者として、長男○○を指定する。」
④付言事項(任意)
付言事項には、法的効力はありませんが、遺言者の思いや家族への感謝の言葉などを記載できます。どのような気持ちで財産の分配方法を決めたのかをメッセージとして記しておくことで、円満な相続につながる場合もあります。
文章例
「私の死後、相続人の皆が仲良く助け合って暮らしてくれることを願っています。妻○○にはこれまでの支えに心から感謝しています。」
⑤日付・署名・押印
遺言書には日付、遺言者の署名、押印が必須です。日付は年月日を明確に記載し、署名は自書、押印は認印でも可ですが実印が望ましいとされます。
文章例
「令和○年○月○日
遺言者 ○○ ○○(署名押印)」
遺言書の作成にあたって準備すべきこと
遺言書を作成するにあたり、事前に準備しておくべきことがあります。適切な準備を行うことで、スムーズに書き進められ、後にトラブルが発生する可能性を減らすことができます。
- 財産の洗い出し
不動産、預貯金、有価証券、動産(自動車や貴金属など)をリストアップし、できるだけ正確に把握しておきます。負債(ローンや借入金など)も忘れずに整理することが重要です。この時、不動産登記事項証明書、通帳、株式の保有証明書などの資料を集めておくと、遺言書の作成や将来の手続きがスムーズになります。また、整理した内容を財産目録としてまとめておくと、後の手続きに役立ちます。 - 相続人・受遺者の確認
法定相続人の範囲を確認し、相続人以外に財産を遺贈したい相手(友人や団体など)がいれば、その氏名や所在を特定しておきます。 - 分配方針の検討
誰に何を渡すのかを考える際には、公平性や実際の利用状況を考慮することが大切です。たとえば、自宅に同居している相続人には自宅を相続させる、事業を継ぐ子には会社関連の財産を集中させる、など具体的に整理します。 - 遺言執行者の検討
遺言内容を確実に実行してもらうために、誰を遺言執行者に指名するかを考えておきます。親族のほか、行政書士や弁護士などの専門家を候補とすることも検討できます。
民法で定められた自筆証書遺言の要件
自筆証書遺言は最も身近で手軽な遺言方式ですが、民法で定められた要件を満たさないと無効になる可能性があります。ここでは、その具体的な要件について解説します。
日付
遺言には日付を明確に記載する必要があります。「令和○年○月○日」と特定の日を記すことが求められ、「○月吉日」や「○月下旬」といった不特定の表現は無効とされます。
署名・押印
遺言者本人が自筆で署名し、押印することが必須です。押印は認印でも可能ですが、偽造防止の観点から実印が推奨されます。署名は必ず遺言者本人の自書でなければなりません。
財産目録
財産目録は、遺言書本体と別に作成して添付することができます。財産目録については自書でなくてもパソコンで作成したり、不動産登記事項証明書や預金通帳のコピーを添付することも可能です。ただし、各ページに遺言者本人の署名と押印が必要となります。
訂正・追加の方法
遺言書の内容を訂正や追加する場合にも、ルールが定められています。具体的には、訂正箇所に二重線を引いて押印し、修正後の文言を記載します。さらに、修正した書類の一番下などの空いている部分に、訂正した旨とその内容を明記し、署名を加える必要があります(例:「上記5行目中、3文字削除6文字追加 ○○(署名)」)。訂正方法が不適切だと、その部分が無効とされる可能性があります。
遺言書の保管方法
遺言書は作成しただけでは安心できず、どこでどのように保管するかが非常に重要です。適切に保管しないと、遺言が見つからなかったり、改ざんや紛失といったトラブルにつながる恐れがあります。
遺言書の保管方法としては、自宅での保管、信頼できる親族に預ける、専門家に預けるなどいくつかの選択肢があります。自宅保管や親族に預ける方法は費用がかからず手軽ですが、紛失や改ざん、発見されないリスクがある点がデメリットであり、さらに相続開始後には必ず家庭裁判所での検認が必要です。行政書士や司法書士、弁護士などの専門家に預ける場合は一定の安心感はありますが、やはり検認を経なければならない点は変わりません。
こうした従来の方法に対し、安全で便利な方法として年々利用者が増加しているのが「法務局での保管制度」です。
法務局での保管とは
自筆証書遺言を法務局に預けて安全に保管することができる制度です。2020年7月にスタートした比較的新しい仕組みで、全国にある312か所の法務局で利用できます。
メリット
法務局での保管制度を利用する最大のメリットは、家庭裁判所での検認手続きが不要になるため、相続開始後の手続きがスムーズに進む点です。また、法務局で厳重に管理されることで、紛失や改ざんのリスクを防止でき、安心して遺言書を残すことができます。さらに、遺言者が死亡した際には相続人が法務局で遺言書の存在を確認できるため、遺言が発見されずに放置されるリスクが低減されます。
注意点
法務局での保管制度を利用するにあたっては、いくつか注意すべき点があります。
まず、遺言書は用紙のサイズや余白などについて定められたルールに従って作成しなければならず、これに反すると受け付けてもらえません。また、文書はスキャンして画像化されるため、ホッチキスなどで綴じ合わせることはできません。さらに、すべてのページに「1/5」「2/5」といったページ番号を記載する必要があります。
加えて、保管後に遺言の内容を変更したい場合には、いったん遺言の返還を受けて破棄した上で、新しい遺言を作成し改めて保管手続きを行うことが求められます。
利用方法
法務局での保管制度の利用方法は、大きく分けて「遺言者が遺言を預ける際の手続き」と「相続開始後に相続人等が行う手続き」の2つがあります。
まず、遺言者が遺言を預ける場合には、以下の流れとなります。
- 保管を希望する自筆証書遺言を、様式に従って作成します。
- 本人が①住所地・②本籍地・③本人が所有する不動産所在地のいずれかを管轄する法務局に出向きます。なお、全国の遺言書保管場所は法務省のホームページにて確認することができます。
また、申請手続きの際は必ず本人が出向く必要があるため、入院中などで外出が難しい場合にはこの制度を利用することができません。 - 保管申請書を提出し、手数料(1通につき3,900円)を納付します。
- 本人確認を受けた後、遺言書を法務局に預け入れ、手続きは完了となります。
一方、相続が発生した場合の手続きは次のとおりです。
- 法務局に「遺言書保管事実証明書」の交付を請求し、保管の有無や保管番号を確認します(請求できるのは法定相続人・受遺者・遺言執行者など)。
- 保管がある場合は「遺言書情報証明書」の交付請求、または原本閲覧の申請を行い、遺言の全文・内容を確認します。この際に、請求者の本人確認書類、被相続人の死亡の記載がある戸籍、そして所定の手数料(1通につき800円)が必要です。
- 法務局保管の自筆証書遺言は検認が不要であるため、取得した証明書を用いて、金融機関の相続手続きや不動産登記、遺贈の履行などに活用します。
遺言書の作成にかかる費用
遺言書を作成する際には、方式によって必要となる費用が異なります。ここでは大きく分けて「法定費用」などの公的な支払いと、「専門家に依頼する際の費用」について解説します。
法定費用など
自筆証書遺言の場合は紙とペンさえあれば作成できますので、特に費用は掛かりませんが、正確な遺言を作成するために書類を取り寄せる際には、下記のような費用が掛かります。
- 戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)の取得費用:450円/1通
- 住民票・印鑑証明書の取得費用:300円程度/1通(自治体により異なる)
- 金融機関の残高証明書:数百~数千円/1通(金融機関により異なる)
- 不動産登記事項証明書の取得費用:600円/1通
また、公正証書遺言の場合には下記にのような費用がかかります。
- 公正証書遺言の作成手数料:公証役場に支払う手数料で、遺言に記載する財産額に応じて決まります。例えば、財産が1,000万円以下であれば11,000円、5,000万円以下であれば29,000円、1億円以下であれば43,000円などと段階的に定められています。さらに、公正証書遺言には証人が2名必要で、知人に依頼すれば費用は不要ですが、公証役場で紹介してもらう場合は1人あたり5,000円〜10,000円程度かかるのが一般的です。
専門家へ依頼する際の費用
専門家に依頼する場合の費用は、依頼先や内容によって大きく異なります。たとえば、行政書士に遺言書の作成サポートを依頼すると、おおむね5万円〜10万円程度が相場ですが、財産の種類や量、内容の複雑さによって変動します。弁護士に依頼する場合は、遺言執行や相続紛争を見越して契約するケースが多く、10万円以上かかることもあり、案件の難易度によってさらに高額となることもあります。また、司法書士に依頼する場合は、不動産登記や相続登記との関連で依頼されることが多く、費用は5万円〜10万円程度が目安です。
遺言書の作成費用は、どの方式を選ぶか、そしてどの専門家に依頼するかによって大きく異なります。自分にとって必要なサポート内容を整理し、適切な方法を選ぶことが大切です。
まとめ
遺言書は、相続をめぐるトラブルを未然に防ぎ、遺族に安心を残すための重要な手段です。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のいずれを選ぶにしても、それぞれに特徴と注意点があり、自分の状況に合った方法を検討することが大切です。
特に、財産が不動産や預貯金などの複数にわたる場合、必要であれば行政書士などの専門家に相談し、自分に最もふさわしい遺言の形を整えていくと安心です。遺言は一度作成したら終わりではなく、ライフスタイルや財産状況の変化に応じて見直すことも重要です。適切な準備と定期的な見直しを重ねることで、遺族にとっても遺言者にとっても納得のいく形で財産を託すことができるでしょう。
関連コラムはこちら↓
遺言書の種類を徹底解説!法的効力の違いや作成時の注意点相続手続きで困ったら行政書士に相談!手続きの流れとサポート内容を詳しく紹介遺言書作成サポートは行政書士におまかせ!法的効力を持つ遺言書のポイント

特定行政書士として、幅広い業界における法務支援やビジネスサポートに従事するとともに、業務指導者としても精力的に活動。企業法務や許認可手続きに関する専門知識を有し、ビジネスの実務面での支援を中心に展開しています。(登録番号:03312913)