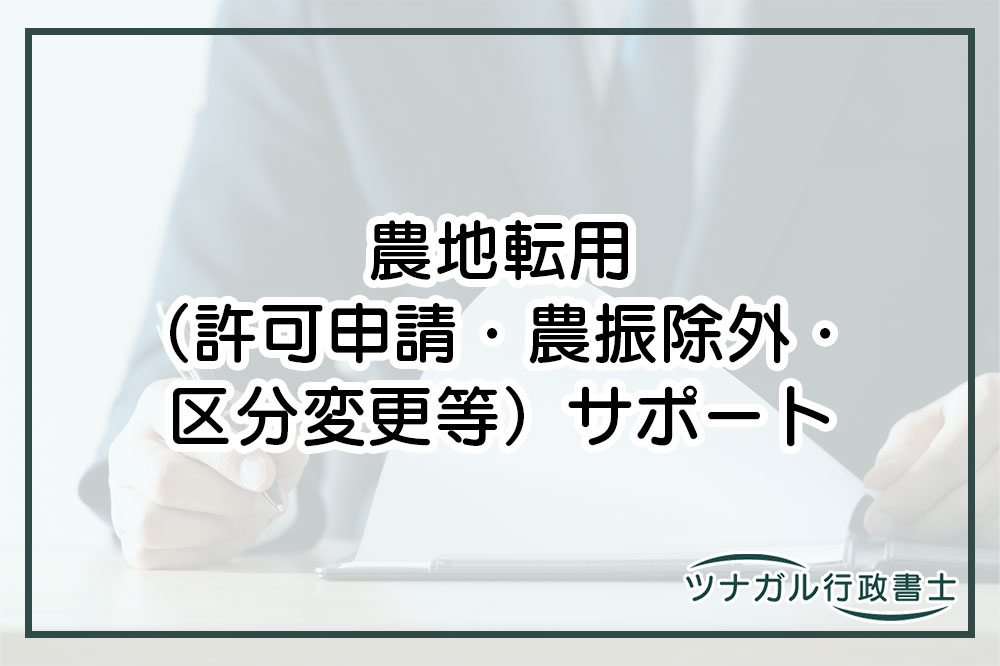料金相場(農地転用(許可申請・農振除外・区分変更))
農地転用(農地法4条、5条届出、農地法4条、5条許可申請)
| 法定手数料 | 報酬代 | 合計金額 | |
| 農地法4条、5条(届出) | 5,000 | 55,000 | 60,000 |
| 農地法4条、5条(許可申請) | 5,000 | 165,000 | 170,000 |
| 農振除外届出 | 5,000 | 220,000 | 225,000 |
| 用途区分変更届出 | 5,000 | 55,000 | 60,000 |
*農地法4条、5条における届出と許可申請の違いは市街化区域内・域外となります
*日本行政書士会連合会の「報酬額統計」を目安に作成
*行政書士報酬代は目安となります
農地転用(許可申請・農振除外・区分変更)とは
農地転用とは、田んぼや畑などの「農地」を、住宅・駐車場・店舗・資材置き場など、農業以外の目的で使うための手続きのことです。農地は国の法律で守られているため、勝手に使い方を変えることはできません。使い方を変えるには、必要に応じて次のような手続きが必要になります。
許可申請とは
農地を農業以外に使う場合は、まず「農地法」に基づく手続きが必要です。手続きには2つのケースがあります。
- 農地法第4条:自分の農地を、自分のために使い方を変えるとき(例:自宅を建てたいとき)
- 農地法第5条:農地を売ったり貸したりして、別の人が使い方を変えるとき(例:事業者に売って駐車場にする場合)
農地法4条、5条届出と農地法4条、5条許可申請の違い
- 届出で済む場合:都市計画で「市街化区域」に指定されている場所などでは、比較的開発が認められており、届出だけで手続きが完了します。
- 許可が必要な場合:それ以外の地域(市街化調整区域など)では、知事や農業委員会などの許可が必要です。許可を受けるには、転用の理由や計画内容が適切であることが求められます。
農振除外届出(農業振興地域から外す手続き)とは
「農業振興地域」に指定されている農地は、そもそも転用ができません。そのため、まずはこの区域から農地を外す「農振除外」の手続きを行う必要があります。
この手続きは年に数回しか受け付けていない自治体もあるため、事前にスケジュールの確認や準備がとても大切です。
用途区分変更届出(用途の区分を変える手続き)とは
土地には「この場所は住宅用」「この場所は工場用」など、用途のルールが決まっています。これを「用途地域」や「土地利用の区分」といいます。
農地転用の際に、こうした用途が希望と合っていない場合は、「区分変更」の手続きをして、使い方を変更できるようにします。
お申込みの流れ
以下は、農地転用のうち、農地法第4条・第5条の許可申請(市街化調整区域など)を行政書士に依頼された場合のお申込みの流れです。
1. 初回相談・ヒアリング
行政書士が転用予定地の場所、現在の利用状況、転用後の用途(建物の建築や造成など)について詳しくヒアリングし、申請の必要性や可否の見通し、スケジュールの大枠をご説明します。
2. 現地調査・関係機関への確認
必要に応じて行政書士が現地を確認し、都市計画や農業委員会、開発指導課など関係機関へ事前相談を行い、申請にあたっての課題や必要資料を洗い出します。
3. 必要書類のご案内・収集サポート
登記事項証明書、公図、事業計画書など申請に必要な書類のリストを提示し、取得方法や作成のポイントをご案内します。収集が難しいものについては行政書士が代理取得または作成をサポートします。
4. 申請書類の作成・内容調整
事業計画や図面の内容を整理し、許可要件に適合する形で申請書類を整えます。必要に応じて土地所有者や事業者間の同意確認も行います。
5. 農業委員会への申請・対応
行政書士が農業委員会に申請を行い、審査過程で求められる補正や追加説明にも対応します。審査結果が出るまでの進捗管理や報告も随時行います。
※市街化調整区域では、開発許可(都市計画法)や他法令の調整も必要な場合があるため、状況によっては連携士業や行政機関との協議を含めたサポートが行われることもあります。
必要書類
以下は、農地法第4条・第5条の「許可申請」(市街化調整区域など)の場合の必要書類例です。
- 許可申請書(農地法第4条または第5条に基づく様式)
- 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
- 地番図・公図
- 現況写真(農地の現状を示すもの)
- 転用事業の計画図(配置図・平面図・造成図など)
- 事業計画書(事業の目的・内容・期間などを記載)
- 案内図(現地の位置と周辺環境が分かる地図)
- 資金計画書(事業に必要な資金の根拠資料)
- 権利関係を証明する書類(所有者でない場合:賃貸借契約書、同意書等)
※各市町村や都道府県の農業委員会により、添付書類の内容や書式、追加資料の要否(例えば、上下水道計画や開発許可関係書類など)に違いがあります。特に、市街化調整区域内では都市計画法との整合性の確認資料が求められることもあります。
案件概要
| 項目 | 内容 |
| サポート内容 | ・転用予定地や計画内容のヒアリング・適用法令の確認 ・現地調査・関係機関(農業委員会、都市計画課など)との事前協議 ・必要書類の収集支援および代理取得(登記簿、公図等) ・許可申請書類一式の作成および内容調整 ・農業委員会への提出および補正・審査対応 |
| 依頼者の業務 | ・計画内容(用途、面積、時期など)の提供 ・必要に応じた関係者(地主や設計士等)との調整 ・実印・委任状の準備と押印 ・一部書類(売買契約書や事業計画など)の提供・確認 |
| 申請期間(目安) | ・農地法4条、5条 届出 申請書提出まで:1週間~10日程度 ※形式的に不備がなければ速やかに受理される。・農地法4条、5条 許可申請 申請書提出まで:2週間~1か月程度 許可取得まで:1.5~2.5か月程度・農振除外 届出 申請書提出まで:1~2か月程度 除外決定まで:3~6か月程度(年2~4回の受付や審査がある自治体が多い)・用途区分変更 届出 申請書提出まで:2週間~1か月程度 変更決定まで:2~4か月程度(農振除外に準ずる対応が必要なケースもある) |
| 対応地域 | 全国オンライン対応可 |
| 相談方法 | メール・電話・オンライン面談可 |
| お支払い方法 | クレジットカード、銀行振込 |
| お支払い金額 | 着手金:報酬の50%(業務開始前) 完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等) |
| お支払い期限 | 着手金:業務開始前にお支払い 完了金:許可取得・納品時にお支払い |
| キャンセル料 | 着手前まで無料 |
行政書士に依頼するメリット
農地を住宅や駐車場、資材置き場などに転用するには、「農地転用許可」や「農業振興地域除外申出(農振除外)」「都市計画法上の区分変更」など、複数の手続きが必要となる場合があります。これらの申請は法律や行政の運用に基づく判断が多く、書類の不備や手続きの順序ミスにより長期化・却下となるケースも少なくありません。
行政書士に依頼すれば、現地や用途の状況に応じて、どの手続きが必要かを的確に判断し、関係機関との事前調整から書類作成、提出まで一括して対応してもらえます。特に、許可を得るためのポイントやスケジュール管理を行政実務のプロが担うことで、無駄なく確実に転用を進めることができます。