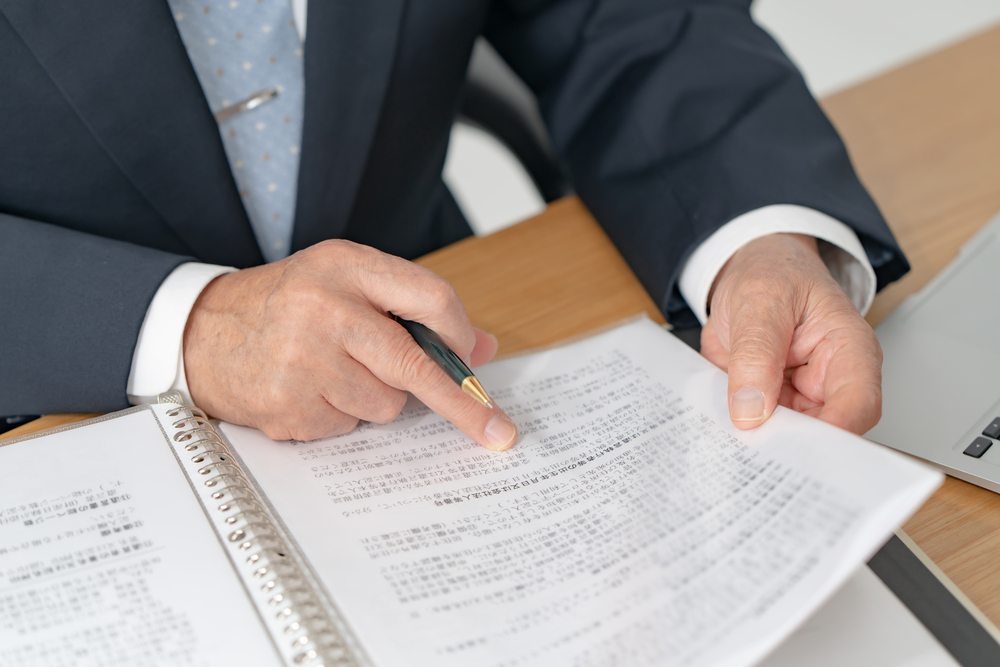目次
相続手続依頼書とは?
銀行などの金融機関では、口座名名義人が亡くなると自動的に凍結され、引き出しや振り込みといった入出金ができなくなります。そのため、相続手続では、金融資産の名義変更や解約を行う際に、相続人の中から代表者を決めて進める必要があります。そのときに使用されるのが「相続手続依頼書」です。
相続手続依頼書の必要な理由とは
相続手続依頼書は、その名のとおり「相続手続きを行うために必要な書類」であり、金融機関などで故人名義の預貯金や有価証券を相続人名義に移す際に用います。相続人全員が「この人に手続きを任せます」という意思を示すために提出するものです。
実務上は、金融機関が用意する専用の書式に必要事項を記入し、相続人全員が署名・押印を行います。これにより相続人全員の合意が確認され、金融機関側で手続きを進めることができます。
相続手続依頼書は「代表者を明確にし、金融機関へ正式に委任の意思を伝えるための書類」であり、相続手続きをスムーズに行う重要なポイントとなります。
金融機関によって異なる名称に注意
相続手続依頼書は金融機関や証券会社ごとに名称が異なる場合があります。事前に確認しておくことが大切です。
【参考】
| 金融機関 | 書類名 |
| 三菱UFJ銀行 | 相続届 |
| 三井住友銀行 | 相続に関する依頼書 |
| みずほ銀行 | 相続関係届書 |
| りそな銀行 | 相続手続依頼書 |
| 横浜銀行 | 相続手続依頼書 |
| ゆうちょ銀行 | 貯金等相続手続請求書 |
| 三菱UFJ信託銀行 | 相続手続依頼書(兼同意書) |
| 野村證券 | 相続手続依頼書 |
いずれの金融機関・証券会社でも、所定の書式を用いて手続きを行う必要があります。中には、法定相続人全員の署名・押印や印鑑証明書の提出を求められるケースもあるため、あらかじめ必要書類を確認して準備しておくとスムーズに進められるでしょう。
相続手続依頼書が必要となる主ななケースは
相続手続依頼書は、主に金融機関や証券会社での相続手続きにおいて必要になります。代表的なケースをカテゴリごとに整理すると次のとおりです。
| 分類 | 主ななケース |
| 預貯金口座 | ・普通預金・当座預金の解約や払い戻し ・定期預金の解約や満期金の受取 ・外貨預金の解約・換金 |
| 証券・投資関連 | ・証券口座(株式・投資信託など)の名義変更 ・証券口座の解約・資産の払い戻し ・国債や社債など有価証券の換金・名義変更 |
| その他金融サービス | ・貸金庫の開扉や解約 ・ローン残高やカード債務の精算 ・年金・保険関連口座の清算 |
金融機関ごとに書式や手順には違いがありますが、いずれも相続人全員の同意を示すために相続手続依頼書を提出し、代表者がまとめて手続きを進めるのが一般的です。
相続手続きの流れと相続手続依頼書の使うタイミングとは
相続手続きを進めるうえで「どのタイミングで相続手続依頼書を使うのか」がわかりにくい方も多いはず。
相続手続は
①死亡届の提出→②遺言書の有無確認→③相続人・相続財産の調査→④遺産分割協議→⑤金融機関や証券会社での名義変更や解約
という流れで進みます。
このうち⑤のタイミングで活躍するのが相続手続依頼書です。金融機関では相続手続きの際に、相続人全員の同意を証明するため相続手続依頼書の提出が必要になります。この書類があれば、相続人全員が金融機関へ出向かなくても代表者が手続きをまとめて行えるため、スムーズな手続きが可能になります。
ただし、依頼書の提出には遺産分割協議書の完成、戸籍謄本や印鑑証明の準備などが必要になりますので、手続きの全体像を意識して準備を整えることが大切です。
預金の相続手続きの流れ(相続手続依頼書の提出を含む)
預金の相続手続きは、金融機関によって細部が異なるものの、基本的な流れは共通しています。ここでは相続手続依頼書の提出を含めた一般的なステップをまとめます。
STEP1:相続発生の連絡
口座名義人(被相続人)が亡くなられた場合、まず取引金融機関に連絡します。その時点で被相続人名義の口座は凍結され、入出金はできなくなります。以後の手続きに関する案内とともに相続手続依頼書が交付されます。なお、相続手続完了前に無断で預貯金を引き出すと、後の遺産分割でトラブルになる可能性があるため注意が必要です。
STEP2:必要書類の準備
遺言の有無や相続の状況によって準備すべき書類が変わります。主なパターンは次のとおりです。
① 遺言書がある場合
- 遺言書(原本、自筆証書遺言の場合は検認済証明書付)
- 相続手続依頼書(金融機関所定)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 遺言執行者の選任審判書謄本(必要な場合)
- 受遺者・遺言執行者の印鑑証明書・実印
- 被相続人の通帳・キャッシュカード等
② 遺言書がない場合(遺産分割協議書あり)
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印)
- 相続手続依頼書(金融機関所定)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 相続人全員の戸籍(発行1年以内)
- 相続人全員の印鑑証明書(発行3か月以内)
- 被相続人の通帳・キャッシュカード等
金融機関によっては書類に有効期限が設定されている場合があるため、発行日にも注意が必要です。
STEP3:必要書類の提出
相続手続依頼書に依頼内容を記入し、必要書類とともに金融機関へ提出します。提出先は支店窓口や相続専門部署など、金融機関によって異なります。
STEP4:払い戻し・名義変更手続き
金融機関での審査が完了すると、払戻しや名義変更が実行されます。提出から払い戻し完了までの期間は通常1〜2週間程度で、書類収集を含めると全体で1か月ほどかかる場合もあります。
相続手続依頼書の入手方法とは
相続手続依頼書は、相続財産の名義変更や解約を進めるうえで欠かせない書類ですが、入手方法は金融機関によって異なります。主に「郵送で取り寄せる方法」と「店舗で直接受け取る方法」の2つがあります。
金融機関から郵送で取り寄せる
相続手続依頼書は郵送で取り寄せることができます。大手銀行や地方銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行など多くの金融機関が郵送対応をしており、電話やウェブサイトから申込みができる場合もあります。まずは故人の口座がある金融機関のコールセンターや店舗に連絡し、相続手続を開始する旨を伝えましょう。その際に「相続手続依頼書を郵送で取り寄せたい」と依頼するとスムーズです。
郵送で届く書類のセットには、相続手続依頼書のほか、遺産分割協議書や相続関係説明図のひな形、必要書類一覧などが同封されているいるのが一般的です。
金融機関によっては「戸籍謄本のコピーを事前に送る必要がある」または「電話で詳細なヒアリングを受ける必要がある」といったケースもありますので、依頼前に確認しておくと安心です。
金融機関の店舗で直接受け取る
時間に余裕がある場合や、早めに手続きを進めたい場合は、金融機関の店舗で直接受け取る方法がおすすめです。窓口で相談しながら受け取れるため、書き方や必要書類についてその場で確認できる点が大きなメリットです。
手続きの際には故人の口座情報を伝えて相続手続の開始を申し出ます。その際、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)や故人の死亡を証明できる戸籍(除籍)謄本などの提示を求められることがあります。
その場で書類の説明を受けられるだけでなく、不明点を直接質問できるのは安心材料ですが、金融機関によっては来店予約が必要な場合もあります。事前に連絡を入れ、必要書類や持参物、予約の有無を確認してから来店すると安心です。
相続手続依頼書の書き方と記入例
相続手続依頼書を入手したあと「これ、どうやって書いたらいいんだろう…」と悩む方は多いです。金融機関から届く書類の中でも記入漏れや誤記が多く、結果的に手続きが遅れてしまう原因にもなりやすいのがこの相続手続依頼書です。ここでは、相続手続依頼書の書き方と記入時の注意点をわかりやすく解説しますので、手続きをスムーズに進めるための参考にしてください。
記入例と注意すべきポイント
まず、相続手続依頼書には以下のような内容を記入するのが一般的です。
- 被相続人(亡くなられた方)の氏名・生年月日・死亡日
- 相続人全員の氏名・住所・連絡先
- 相続手続の代表者(手続代理人)となる方の氏名・住所・連絡先
- 相続財産の内容(預貯金口座の情報など)
- 相続人全員の署名と実印の押印
金融機関によって様式は異なりますが、「相続人全員の署名押印」が必要なのは共通です。代表者だけが記入すればよいと思いがちですが、相続人全員が同意していることを金融機関が確認するため、全員の実印が必要で、印鑑証明書の提出も求められるケースが多い点に注意しましょう。
記入例としては、金融機関から送られてくる「記入見本」を確認しながら進めましょう。
さらに、記入時の注意ポイントとして以下の点を意識しましょう。
- 住所・氏名は住民票・戸籍の記載どおりに正確に記載する(アパート名・部屋番号、旧字体なども含めて)
- 口座情報は支店名・口座番号・口座名義を正確に記載する
このような細かな表記ミスがあると手続きが差し戻されることもあります。そのため、住民票や戸籍謄本を参照しながら丁寧に記入することが大切です。
相続手続依頼書を使う際に4つの注意点
相続手続依頼書は提出すれば終わりではなく、いくつかの注意点を押さえておく必要があります。不備があると手続きが止まってしまうため、次の点を必ず確認しましょう。
① 相続人全員の署名・実印の押印
相続人が複数いる場合は、相続人全員が署名し、実印を押すことが必須です。一人でも欠けると金融機関で手続きが進められません。印鑑証明書の添付も必要となるケースがほとんどですので、有効期限内のものを揃えておきましょう。また「代筆」や「押印の省略」は後のトラブルにつながるため絶対に避けてください。
② 通帳や証書を紛失している場合
被相続人の通帳や証書を紛失している場合は、依頼書の該当欄にその旨を記載します。口座番号が分からない場合や、そもそもどの金融資産を持っていたか不明な場合は、まず金融機関に照会を依頼して確認しましょう。預貯金だけでなく投資信託や貸金庫などが見つかることもあります。
③ 金融機関ごとに必要書類が異なる
相続手続依頼書のほかに、遺産分割協議書や戸籍謄本、被相続人の住民票除票などを提出しなければならない場合があります。必要書類は金融機関によって異なるため、必ず事前に確認し、不備のないように準備を進めてください。
④ 住所・氏名の記載は正確に
依頼書に記載する住所や氏名は、住民票や戸籍と完全に一致していなければなりません。アパート名の省略や漢字の誤りがあると差し戻しになることがあります。面倒でも公的書類を見ながら丁寧に記入することが重要です。
このように、相続手続依頼書は相続人の同意を示す便利な書類ですが、不備があるとスムーズに進まなくなります。注意点をしっかり確認し、金融機関とも相談しながら準備を整えることが安心につながります。
相続手続きで行政書士に依頼するメリットとは
相続手続依頼書を使って金融機関で手続きを進める際、「書類の集め方がわからない」「書き方に自信がない」という方も多いのではないでしょうか。そんなときに頼れる存在が行政書士です。
行政書士に依頼するメリットは、相続人調査・相続関係説明図・遺産分割協議書の作成から金融機関の相続手続依頼書の記入サポートまで、一連の手続きをまとめてサポートできることです。
手続きを間違えると差戻しになり、時間も精神的な負担も大きくなりますが、行政書士へ依頼することで書類の不備や記入漏れのリスクを減らせ、相続手続きをスムーズに進められるのが大きなメリットです。
相続手続依頼書を提出するためには印鑑証明書や戸籍謄本の取得も必要になりますが、行政書士はこれらの取得代行も行えますので、ご家族の負担軽減にもつながります。
まとめ
相続手続依頼書は、金融機関での名義変更や解約に欠かせない重要な書類です。しかし、記載内容の誤りや必要書類の不足があると、手続きが止まり、大幅に時間がかかることもあります。
行政書士へ相談することで、必要書類の収集から依頼書の記載サポートまで任せられ、安心して確実に手続きを進められます。ご家族の負担を減らし、スムーズに相続を完了させるためにも、不安を感じたらまずは行政書士へ相談してみることをおすすめします。

特定行政書士として、幅広い業界における法務支援やビジネスサポートに従事するとともに、業務指導者としても精力的に活動。企業法務や許認可手続きに関する専門知識を有し、ビジネスの実務面での支援を中心に展開しています。(登録番号:03312913)