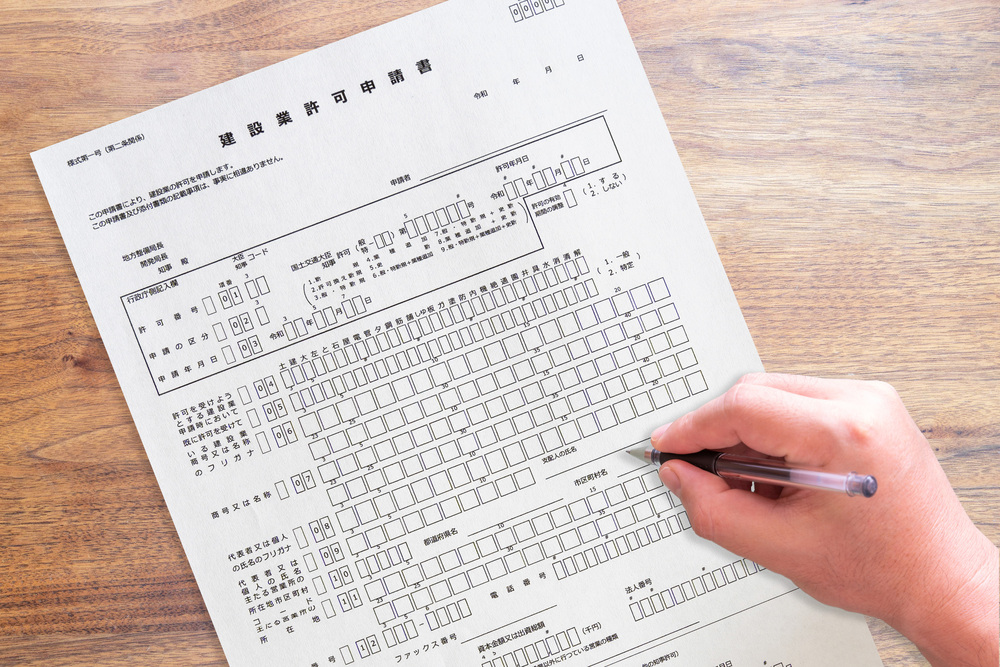目次
建設業許可ってなに?まず知っておきたい基本
「建設業を始めたいけど、許可って本当に必要なの?」と思う方も多いかもしれません。建設業許可とは、一定以上の規模の工事を請け負うときに法律で義務付けられている、いわば“建設業を営むためのライセンス”です。許可を持っていることで取引先からの信頼が高まり、公共工事や大きな案件を受注できるチャンスも広がります。
この制度は「建設業法」という法律で定められており、目的は手抜き工事や資金トラブルを防ぎ、業界全体の健全な運営を守ることにあります。つまり、許可を持っているかどうかは依頼主にとって安心できる基準であり、事業者にとっても社会的な信用につながる大切なポイントです。
建設業法と許可の役割
建設業法では、一定金額以上の工事を受注する場合に必ず建設業許可が必要とされています。もし無許可で営業すると罰則の対象になるため注意が必要です。逆に許可を持っていれば、公共工事への参加や入札などで有利になります。
「一般建設業」と「特定建設業」の違い
建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」の2種類があります。区分は元請として下請に発注する金額で決まり、一定規模以上を下請に任せる場合は「特定建設業」の許可が必要です。
具体的には、元請として下請契約の合計が一般工事で5,000万円以上、建築一式工事で8,000万円以上になる場合に特定建設業の許可が必要とされています(2025年2月1日施行の改正基準)。一般建設業は中小規模の工事に幅広く対応し、特定建設業は主に大規模工事を元請として行う場合に求められるものです。
どんなときに建設業許可が必要になる?
建設業の仕事をするからといって、必ずしも最初から「建設業許可」が必要になるわけではありません。ポイントとなるのは、工事の規模や契約金額です。「どのくらいの金額から許可が必要になるのか?」「許可がいらない工事はあるのか?」を整理してみましょう。
許可が必要となる工事の目安
建設業法では、請け負う工事の金額によって許可の要否が決まります。次の基準を超える場合は、必ず建設業許可が必要です。
- 建築一式工事の場合:税込1,500万円以上、または延べ面積150㎡を超える木造住宅工事
- 建築一式以外の工事の場合:税込500万円以上
例えば、リフォーム工事で600万円の契約を結んだ場合、小規模事業者であっても許可が必要になります。反対に、基準未満の金額であれば許可がなくても工事は可能です。ただし、500万円ギリギリの案件が続くときは、金額の管理をしっかり行う必要があります。
また、判断基準となる金額は「材料費込み・税込金額」です。「材料は施主が用意するから大丈夫」と思いがちですが、工事全体の請負金額で判定される点に注意しましょう。
許可が不要なケース
一方で、すべての工事に許可が必要なわけではありません。次のような場合は例外とされています。
- 税込500万円未満の小規模な工事
- 自分の建物を自分で工事する「自家施工」
ただし、許可が不要な場合でも契約書を作成する義務や、工事後の瑕疵担保責任(欠陥への対応責任)は残ります。さらに、公共工事や元請けとしての受注を目指すなら、早めに許可を取得しておくことが将来の安心につながります。
建設業許可と資格のポイント
「建設業許可を取るには資格がないとダメなの?」とよく質問をいただきます。実は、建設業許可で求められるのは必ずしも国家資格だけではありません。一定の経営経験や実務経験があれば条件を満たせるケースも多いのです。ここでは、許可取得に欠かせない2つの重要な役割について解説します。
経営業務の管理責任者(経管)とは?
一つ目は「経営業務の管理責任者(経管)」です。これは、会社を安定して経営できる人がいるかを確認するための要件です。特別な資格は不要ですが、建設業に関する経営経験が求められます。
- 法人の場合:取締役として5年以上、建設業の経営に携わった経験がある人
- 個人事業主の場合:事業主として5年以上の経営経験がある人
また、「2年以上の経営経験+役員経験」などの補助的な要件で認められるケースもあります。つまり、資格よりも「どのような経歴を持っているか」が大切になる部分です。
専任技術者の資格・経験とは?
二つ目は「専任技術者」です。これは工事の技術面をしっかり管理する役割で、営業所ごとに必ず1名配置しなければなりません。許可業種に応じて、国家資格や実務経験が必要です。
代表的な国家資格は以下のとおりです。
- 建築士(1級・2級)
- 施工管理技士(1級・2級)
- 電気工事士 など
資格があれば実務経験の証明は不要で、スムーズに要件を満たせます。一方で、資格がなくても「10年以上の実務経験」があれば専任技術者と認められる場合があります。また、建築系の学科を卒業して一定の実務経験を積むことで要件を満たす方法もあります。
監理技術者が必要となるケース
さらに、2025年2月1日以降の改正により、請負金額が一般工事で4,500万円以上、建築一式工事で9,000万円以上の場合は「監理技術者」を専任で配置することが義務化されました。監理技術者になるには、施工管理技士などの国家資格に加えて「監理技術者講習」を修了している必要があります。
このように、建設業許可で求められるのは「経営を管理できる人」と「技術を管理できる人」の二本柱。資格だけでなく、経歴や経験の証明も重要なポイントになるのです。
建設業許可を取るために必要な4つの条件
「建設業許可って、申請すれば誰でも取れるの?」と疑問に思う方も多いと思います。実際には、国が定めた4つの条件をクリアしなければ許可は下りません。これは、建設業を安心・安全に運営するための基準でもあります。ここでは、その4つの条件をやさしく解説します。
1. 経営を任せられる責任者がいること
建設業を安定して経営できる人が会社にいるかどうかを確認されます。これが「経営業務の管理責任者(経管)」で、法人では取締役、個人事業では事業主として一定年数の経営経験を持っている必要があります。
2. 技術を管理できる人がいること
工事の品質や安全を守る「専任技術者」を営業所ごとに配置する必要があります。建築士や施工管理技士などの国家資格者、または長年の実務経験者が対象です。
3. 安定して工事を行える資金があること
建設業は工事の着手時に大きなお金が動くため、会社に一定の資金力があるかどうかもチェックされます。
- 一般建設業:自己資本500万円以上、または同額の資金を調達できる力
- 特定建設業:自己資本4,000万円以上など、より高い基準
決算書や残高証明などで証明する必要があるため、資金準備も欠かせません。
4. 信用を損なう経歴がないこと
最後に必要なのは「欠格要件に当てはまらないこと」です。社会的信用を欠く人物が経営に関わっていないかどうかが審査されます。
- 過去に建設業法違反で処分を受けていない
- 禁錮以上の刑を受けていない
- 暴力団関係者がいない
この4つの条件を満たすことが建設業許可を取るための大前提です。特に初めて申請する方は「経管は誰になる?」「専任技術者の資格や経験はある?」といった部分を早めに確認しておくと、スムーズな取得につながります。
建設業許可を取るまでの流れ
「建設業許可って、どうやって取るの?」と気になる方も多いと思います。初めての申請だと「役所に何度も行かないといけないのでは?」と不安になるかもしれませんが、ポイントを押さえて準備すればスムーズに取得できます。ここでは、建設業許可の一般的な流れを4つのステップに分けてわかりやすく解説します。
STEP1:事前相談と必要書類の準備
まずは条件の確認と必要書類の準備から始めます。建設業許可は「経営業務の管理責任者」「専任技術者」「資金状況」などを証明する書類が必要です。
特に多いのが、証明書類の不足や整合性の不備による差し戻し。そこで大切なのが行政書士など専門家への相談です。自社に必要な書類を整理でき、申請ミスも防ぎやすくなります。準備に時間がかかることもあるので、早めの行動がカギです。
STEP2:申請先を確認する
建設業許可の申請先は、営業所の所在地や事業の範囲で変わります。
- 一つの都道府県内で営業する場合 → 知事許可
- 複数の都道府県に営業所を持つ場合 → 国土交通大臣許可
提出先は各都道府県の建設業課や土木事務所です。自治体によって提出部数や添付書類に細かい違いがあるため、事前確認を忘れないようにしましょう。
STEP3:申請から審査までの流れ
申請書が受理されると、役所での審査に入ります。特に問題がなければ、通常は30日〜45日程度で許可が下ります。
- 知事許可の場合:約1〜1.5か月
- 大臣許可の場合:約2〜3か月
もし不備があれば補正や追加説明を求められることもあるので、役所からの連絡にはすぐ対応できる体制を整えておくと安心です。
STEP4:取得後の更新・変更手続き
許可は取得して終わりではなく、定期的な更新や届出が必要です。具体的には、毎年の事業年度終了届や5年ごとの更新申請、役員・営業所・技術者の変更時の届出などを行う必要があります。
このように、建設業許可は「事前準備→申請→審査→維持管理」という流れで進んでいきます。初めての方は専門家に相談しながら進めることで、安心して許可取得を目指すことができます。
建設業許可取得で気をつけたいポイント
「建設業許可を取るとき、どんなことに注意すればいいの?」とよくご相談をいただきます。実際、手続きを進めてから思わぬミスが発覚し、再提出や審査の遅れにつながるケースも少なくありません。ここでは、申請前に知っておきたい注意点と、取得後に大切な管理のポイントをわかりやすく整理しました。
よくある申請ミスと防止策
建設業許可の申請で多いトラブルは「書類の不備」です。特に次のようなミスは頻発します。
- 経営業務の管理責任者や専任技術者の証明期間が不足している
- 決算書類の内容に整合性がない(貸借対照表と損益計算書の不一致など)
- 印鑑証明書や登記簿謄本などの有効期限切れ書類を提出してしまう
こうした不備は、申請前にしっかりチェックすれば防げます。特に「経管」や「専任技術者」の経歴・資格が申請業種に対応しているかは重要な確認ポイントです。
事前に行政書士などの専門家に書類を確認してもらうと、こうしたミスを未然に防ぎやすく、一度でスムーズに許可を取れる可能性が高まります。
取得後に必要な管理とルール
許可が下りても、それで終わりではありません。取得後には継続して次のような手続きや管理が求められます。
- 毎年の事業年度終了届(決算報告)の提出
- 役員や営業所、専任技術者の変更時には変更届を提出
- 5年ごとの更新申請を忘れずに行う
- 無許可工事や下請法違反など、法令遵守を徹底する
特に注意したいのは「事業年度終了届の提出忘れ」。これを怠ると、次回の更新で慌てる原因になります。変更事項が出た場合も、原則2週間〜30日以内に届出が必要です。
最近の法改正にも注意
2024年12月13日の法改正により、主任技術者や監理技術者、専任技術者が条件付きで複数現場を兼務できるようになりました。具体的には、請負代金が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)の工事であれば、最大2現場まで兼務可能です。これにより、中小規模の事業者も技術者の配置に柔軟性を持たせやすくなりました。
ただし、許可を持っていない業種の工事を請け負うと無許可営業とみなされるリスクがあります。定期的に社内で確認し、必要に応じて専門家と連携することで、安心して事業を続けられる体制を整えましょう。
まとめ
建設業許可は、建築業を安心して続けるための大切なライセンスです。許可を持つことで公共工事や大きな案件にも挑戦でき、取引先からの信頼も高まります。
取得のためには、経営業務の管理責任者や専任技術者の配置、資金力、信用面など、国が定める条件をクリアすることが必要です。資格だけでなく、経歴や実務経験でも要件を満たせる場合があるため、自社の状況を早めに確認しておくと安心です。
また、許可を取った後も毎年の決算報告や変更届、5年ごとの更新といった手続きが欠かせません。法改正によってルールが変わることもあるため、常に最新の情報をチェックし、必要に応じて専門家と連携して対応することが大切です。
「取得」だけでなく「維持管理」まで見据えて取り組むことが、安定した経営への第一歩です。しっかり準備を整え、安心して建設業を発展させていきましょう。

特定行政書士として、幅広い業界における法務支援やビジネスサポートに従事するとともに、業務指導者としても精力的に活動。企業法務や許認可手続きに関する専門知識を有し、ビジネスの実務面での支援を中心に展開しています。(登録番号:03312913)