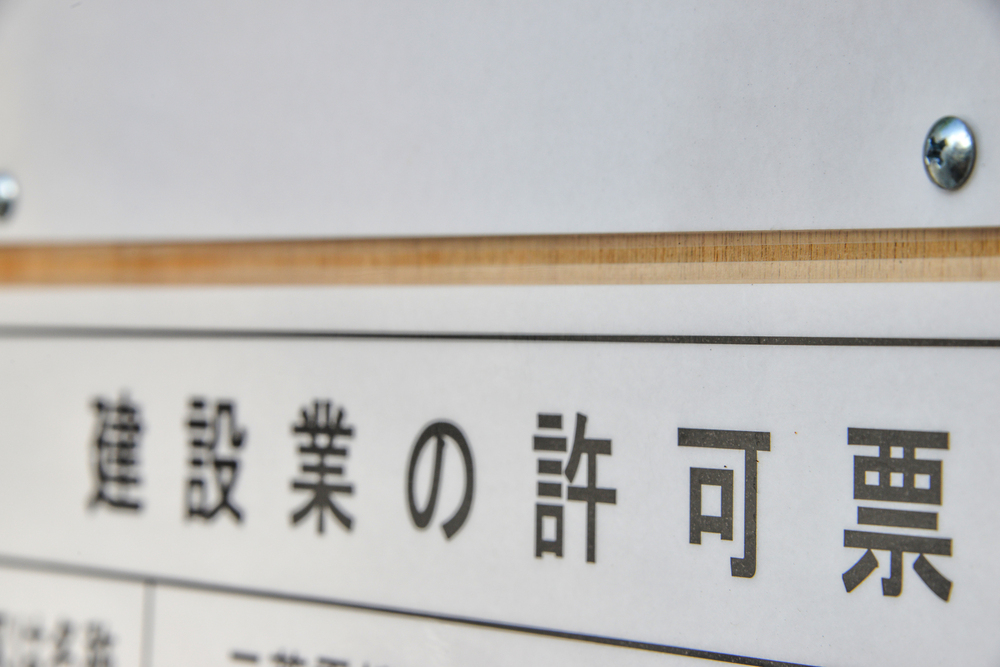目次
そもそも建設業許可とは?
建設業許可とは、一定規模以上の工事を請け負うために、国や都道府県から受ける営業許可のことです。これを取らずに工事を行うと、法律違反となり罰則の対象になります。許可は事業の信頼性向上や取引拡大にもつながる、大切な資格です。
建設業法では、1件あたり税込500万円以上の工事(建築一式工事は1,500万円以上、または延床面積150㎡を超える木造住宅)を行う場合に許可が必要とされています。小規模なリフォームは許可なしでも可能ですが、事業が成長して大型案件を受注する際には許可が必要になる場合があります。予期せぬチャンスに備えて、早めに準備しておくと安心です。
どんなときに建設業許可が必要?
以下の際に建設業許可が必要です。
-
- 工事金額(税込)が500万円以上(建築一式は1,500万円以上)
- 木造住宅で延床面積が150㎡を超える場合
- 元請・下請を問わず継続的に工事を受注する場合
- 公共工事の入札や受注を目指す場合
大臣許可と知事許可の違い
建設業許可は営業所の所在地によって次の2種類に分かれます。
- 大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所がある場合
- 知事許可:1つの都道府県内だけで営業する場合
例)東京都内のみで営業 → 知事許可、東京都と埼玉県の両方に営業所 → 大臣許可。 許可の種類を間違えると再申請が必要になることもあるため、事業計画に合わせて選びましょう。
建設業許可を取るための5つの条件
建設業許可を取得するには、5つの条件をすべて満たす必要があります。どれか1つでも欠けると許可は下りないため、事前に確認しておくことが大切です。
1. 経営業務管理体制があること
建設業の経営を安定して行える体制が必要です。具体的には、建設業で5年以上の経営経験がある役員や、経営に関わる経験者が在籍していることが条件です。経験が足りない場合は、外部から経験者を役員に迎えることで要件を満たせる場合があります。
2. 専任技術者を配置していること
各営業所に常勤の専任技術者を置く必要があります。対象となるのは、1級・2級施工管理技士や建築士などの資格保有者、または10年以上の実務経験者です。資格や経験を満たす人材がいない場合は、新たに採用するか、常勤勤務できる有資格者を確保することで対応可能です。他の会社と兼任している場合は専任とは認められないため注意が必要です。
3. 誠実に業務を行っていること
過去に重大な法令違反や契約違反があると許可は下りません。たとえば、詐欺・横領・背任などで一定期間内に罰金刑以上を受けた場合や、工事で重大な契約違反を起こした場合などが該当します。
4. 一定の資金力があること
安定した工事運営のため、自己資本500万円以上または同額以上の資金調達能力が必要です。新しく会社を作る場合は、資本金を500万円以上に設定しておくとスムーズです。
5. 欠格要件に該当しないこと
申請者本人や役員が禁錮以上の刑を受けてから一定期間経過していない場合や、暴力団関係者である場合などは許可を受けられません。
このように、経営体制・技術者・誠実性・資金力・欠格要件の不該当という5つの条件を満たすことが、建設業許可取得の必須条件です。事前に確認・準備しておけば、許可取得のハードルはぐっと下がります。
条件をクリアするためのポイント
建設業許可の5つの条件を聞くと、「うちでも本当に取れるのかな…」と不安になる方もいるかもしれません。 しかし、重要なポイントを押さえて準備すれば、多くの場合クリアは可能です。 ここでは、特に申請でつまずきやすい「経営業務管理体制」「専任技術者」「資金力」の3つについて、実現方法をわかりやすく解説します。
1. 経営業務管理体制の整え方
経営業務管理体制とは、建設業の経営を適切に行うための経験や人員体制のことです。
- 法人:取締役などの役員として5年以上の建設業経営経験がある人を置く
- 個人事業主:本人または家族従事者が5年以上の建設業経営経験を持つ
- 経験が足りない場合:外部から経験者を役員に迎えて要件を満たす
証明書類(経歴証明や契約書など)を整理すれば、思ったよりスムーズに条件を満たせるケースも多いです。
2. 専任技術者の確保方法
専任技術者は、営業所ごとに常勤で配置する必要があります。 なれる条件は以下のいずれかです。
- 1級・2級施工管理技士、建築士などの国家資格を持つ
- 学歴と実務経験の組み合わせ(例:高校卒+5年、大学卒+3年)
- 許可業種で10年以上の実務経験
他社との兼任は不可なので、常勤で勤務できる人を確保しましょう。要件確認と証明書類の準備は早めが安心です。
3. 資金面の条件を満たすには
申請には、自己資本500万円以上または同額以上の資金調達能力が必要です。
- 法人設立時は資本金を500万円以上に設定
- 既存事業者は最新の決算書で自己資本を確認
- 不足する場合は増資や銀行残高証明で対応
資金要件は事前準備でクリアしやすいため、早めに数値を確認しておきましょう。
この3つのポイントを押さえて書類を揃えれば、建設業許可の条件クリアは十分可能です。許可取得後は大手との取引や公共工事への参入など、新たなビジネスチャンスが広がります。
まとめ
建設業許可を取得すると、500万円以上の工事や公共工事を正式に受注できるようになり、取引先からの信頼も高まります。結果として、受注できる案件の幅が広がり、事業の成長にもつながります。
許可取得の鍵は、必要な条件と申請の流れをしっかり理解し、計画的に準備を進めることです。一つひとつの要件を確認しながら書類を揃えていけば、初めての方でも十分クリアできます。
今のうちから準備を始めれば、チャンスが訪れたときにすぐ行動できます。建設業許可を手にして、安定した経営とさらなる飛躍への一歩を踏み出しましょう。

特定行政書士として、幅広い業界における法務支援やビジネスサポートに従事するとともに、業務指導者としても精力的に活動。企業法務や許認可手続きに関する専門知識を有し、ビジネスの実務面での支援を中心に展開しています。(登録番号:03312913)